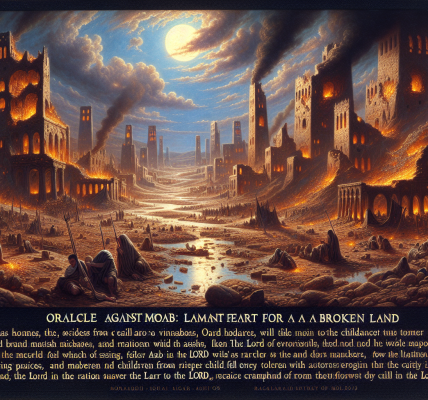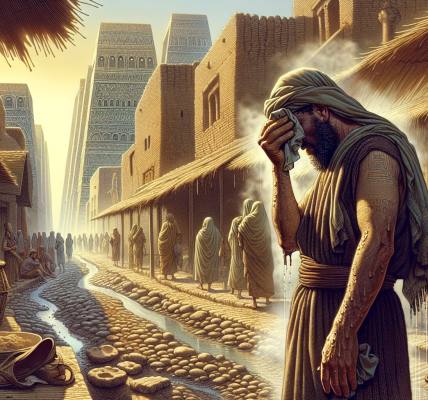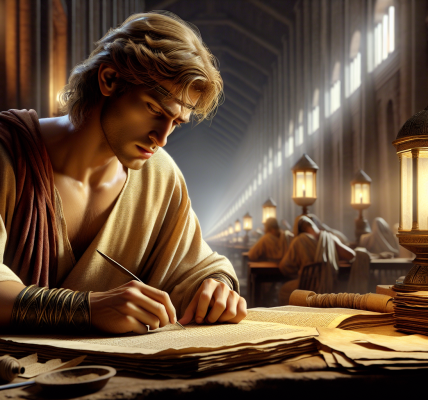マタイによる福音書19章に基づく物語を、詳細で生き生きとした描写を用いて、神学的な正確さを保ちながら語ります。
—
イエスがガリラヤを去り、ユダヤの地に入られたとき、大勢の群衆が彼に従ってきました。その中には、病を癒してもらおうとする者、教えを聞こうとする者、そして単に彼の奇跡を見たいと思う者たちが混じっていました。イエスは彼らを憐れみ、彼らのために教えを説き、癒しの御業を行われました。
ある日、ファリサイ派の人々がイエスのもとにやって来て、彼を試そうとして尋ねました。「先生、人が妻を離縁するのは、どんな場合でも許されるのでしょうか。」彼らの質問は、イエスを罠にかけ、彼の教えに矛盾を見つけ出そうとする意図がありました。
イエスは彼らの心を見抜き、静かに答えられました。「あなたがたは、創造の初めから、『神は人を男と女に造られた』と読んだことがないのか。そして、『それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる』と書かれている。だから、もはや二人ではなく、一体である。だから、神が結び合わせたものを、人が引き離してはならない。」
ファリサイ派の人々はさらに詰め寄りました。「では、なぜモーセは、離縁状を渡して妻を離縁することを命じたのですか。」
イエスは彼らに言われました。「モーセがあなたがたに離縁状を書くことを許したのは、あなたがたの心がかたくなであったからだ。しかし、初めからそうではなかった。わたしはあなたがたに言う。だれでも、不品行以外の理由で妻を離縁して他の女を妻にする者は、姦淫を行うのである。」
弟子たちはこの教えを聞いて驚き、イエスに言いました。「もし夫と妻の関係がそんなに大切なら、結婚しない方がいいのではないでしょうか。」
イエスは彼らに言われました。「この言葉を受け入れることができるのは、すべての人ではない。ただ、それを与えられた者だけが受け入れることができる。ある人は生まれつき結婚できない者もいれば、人によって結婚できないようにされた者もいる。また、天の国のために自ら結婚しない者もいる。これを受け入れることができる者は、受け入れなさい。」
そのとき、人々が子どもたちを連れて来て、イエスに手を置いて祈っていただこうとしました。弟子たちは彼らをたしなめましたが、イエスは言われました。「子どもたちをわたしのところに来させなさい。彼らを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。」そして、イエスは子どもたちに手を置き、祝福してからそこを去られました。
その後、一人の青年がイエスのもとに来て、ひざまずいて尋ねました。「先生、永遠の命を得るためには、どんな善いことをすればよいのでしょうか。」
イエスは彼に言われました。「なぜ、善いことについてわたしに尋ねるのか。善い方はただひとり、神だけである。もし命を得たいのなら、掟を守りなさい。」
青年は尋ねました。「どの掟ですか。」
イエスは答えられました。「殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また、隣人を自分のように愛しなさい。」
青年は言いました。「そういうことはみな、子供の時から守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。」
イエスは彼を見つめ、慈愛に満ちた目で言われました。「もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになる。それから、わたしに従いなさい。」
青年はこの言葉を聞いて悲しみながら去って行きました。彼は多くの財産を持っていたからです。
イエスは弟子たちに言われました。「まことに、あなたがたに言う。金持ちが天の国に入るのは難しい。また、金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。」
弟子たちは非常に驚き、言いました。「それでは、だれが救われることができるのでしょうか。」
イエスは彼らを見つめて言われました。「人にはできないことも、神にはできる。神にとっては、すべてが可能である。」
すると、ペトロがイエスに言いました。「このとおり、わたしたちは何もかも捨てて、あなたに従ってきました。では、わたしたちは何を得るのでしょうか。」
イエスは彼らに言われました。「まことに、あなたがたに言う。わたしに従う者は、新しい世に至るまで、百倍の報いを受け、永遠の命を受け継ぐであろう。しかし、多くの先の者が後になり、後の者が先になる。」
この言葉を聞いて、弟子たちは深く考え込んだ。イエスの教えは、彼らの理解を超えるものであり、同時に、神の国の奥深さを示すものでした。
—
この物語は、イエスの教えが当時の社会通念や人々の期待を超えるものであることを示しています。結婚、富、そして神の国についてのイエスの言葉は、弟子たちや群衆にとって驚きであり、同時に深い信仰の問いかけでもありました。イエスは、神の御心に従うことの大切さを説き、それに従う者には永遠の命が約束されていることを示されたのです。