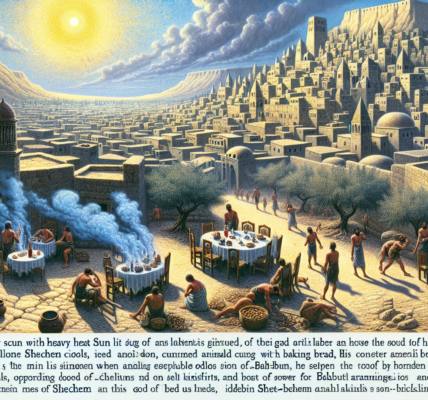荒れ野の風が、乾いた岩肌をむしるように吹き抜ける。セイルの山々は夕陽に赤く染まり、まるで古傷がうずくかのようだった。預言者は痩せた腕を外套に包み、裂けた皮革の靴で礫を踏みしめた。彼の目には、この土地に積もった憎しみの記憶が映っている。
「お前は永遠の憎しみをもってイスラエルの子らを剣で追い立て、災いの時に罪を負わせた」
風が渓谷でうなるように、主の言葉が預言者の内側に湧き上がってきた。彼は岩陰に腰を下ろし、羊皮紙を広げる。硯の水は砂漠の空気ですぐに濁った。
セイルの民はかつて、兄弟の苦難を嘲笑った。エルサレムが崩れ落ちるのを見て、喉を震わせて笑い、「二つの国は我々のものだ」と呟き合った。彼らは荒れ野のハゲワシのように、死肉を啄ばむことを願った。しかし主は言われる。彼らの笑いはやがて自分たちを呑み込む苦い水となると。
預言者の筆先が震える。インクが羊皮紙に滲む。「お前が喜んだすべての地で、わたしはお前を荒れ果てたものとする」。彼は遠くで砂塵が舞い上がるのを見た。まるでかつてエドムの軍勢が蹂躙した町々の記憶が、風に巻き上げられているようだった。
「山々も丘も、谷も荒地も、すべての高き場所で血が流される」。預言者は突然、幼い日に聞いた話を思い出した。祖父が炉辺で語ってくれた、兄弟たちが争い合った最初の日々のことを。エサウとヤコブ。その子孫であるエドムとイスラエル。憎しみは代々受け継がれ、やがて岩のように硬化した。
夕闇が迫り、山肌の赤みが深まる。預言者は立ち上がり、渓谷に向かって叫んだ。「主は言われる。わたしは生きている。お前が憎しみのうちに扱ったように、わたしはお前に扱う」。その声は岩に跳ね返り、幾重にもこだました。
やがて完全な闇が訪れた時、預言者は最後の言葉を書き記した。「そして、わたしが主であることを知るようになる」。羊皮紙を巻き終えると、遠くで山犬の遠吠えが聞こえた。それは、やがて訪れる寂寥の前奏曲のように響いた。
翌朝、預言者が宿営に戻る道すがら、セイルの山々はいつもよりひときわ赤く見えた。それは夕焼けではなく、流される血の色を予感させる赤だった。彼の背後で、不気味な静寂が山全体を覆い始めていた。