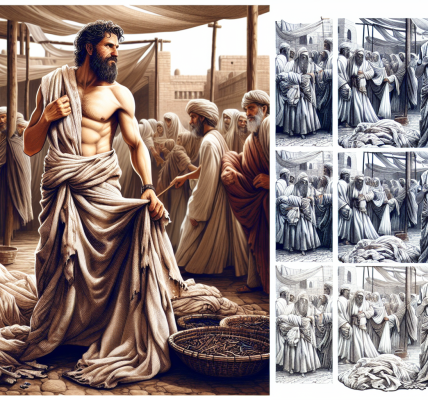その日、風は熱く、オリーブの葉は微かに震えていた。アナニアは、ひび割れた土の縁に腰を下ろし、遠くに広がる荒れ野を見つめていた。彼の背後には、寂れたユダの村が寄り添うようにして立っている。七十歳を越えた老いの骨は、この数年来の重苦しい空気を、ひとつひとつ覚えているように疼いた。バビロンという名は、今や風にのってやって来る不吉な噂そのものだった。人々は、目に見えぬ圧力に胸を押し潰され、神殿の崩れた石のように、希望というものを口にしなくなっていた。
彼は無意識に、足元の埃を払うように手を動かした。すると、乾いた土の中から、小さな陶器の欠片が現れた。かつては水を満たしていただろう壺の、取っ手の一部だ。それを掌に載せてみると、ほのかに涼しい。この土地の記憶は、いつもこんなふうに、断片となって現れる。彼の父も、祖父も、この欠片のように、何か大きなものの一部分としてここに生き、そして消えていった。その大きなものの意味が、今、揺らいでいるのだ。
突然、背後から近づく足音がした。若い羊飼いのエリアキムが、額に汗を光らせて走ってくる。彼の目には、よくあるような諦めの色ではなく、一種の興奮が踊っていた。
「アナニア様、聞きましたか? 集会の場で、イザヤの言葉が読まれたのです。新しい言葉が、写本として回ってきたと。」
アナニアはゆっくりと振り返った。集会といっても、今は広場の片隅で細々と行われる祈りの集いに過ぎない。「イザヤの…か。」 彼はかつて、エルサレムで耳にした、あの荘厳な預言者の言葉を思い出す。それは雷のようであり、また時には子をあやすような細やかな声でもあった。
「何と言っていた? その言葉を。」
エリアキムは息を整え、記憶をたどりながら言葉を紡いだ。「…『もろもろの島よ、わたしの前に黙せ。もろもろの民よ、新たに力を得よ。近づいて語るがよい。われら共にさばきに臨もう』…そんな風に始まるのです。」
風が一瞬強まり、オリーブの林がざわめいた。アナニアの胸中で、長い間眠っていた何かが、ゆっくりと目を覚ます音がした。彼は立ち上がり、腰の痛みを感じながらも、集会が行われるという広場の石段の方へ歩き始めた。足取りは重かったが、心はまるで遠くの光を探すように、前に引かれていた。
広場には、十人ほどの人々が集まっていた。顔には疲労と不安の色が濃い。その中心にいたのは、かつて神殿に仕えていた老祭司ヨナタンだった。彼の手には、羊皮紙の巻物がある。ヨナタンの声は、長い沈黙と悲しみに澱んでいるが、その言葉自体は、古い武具を研ぐような、鋭い輝きを放っていた。
「…『だれが東から人を起したのか。』」 ヨナタンが読み上げる声は、だんだんと力強さを取り戻していく。「『彼は公義をもって呼び求める。彼の足もとに国々を渡し、彼のために王たちを治めさせる。彼らの剣は塵のように、彼らの弓は散らされる籾殻のようになる…』」
アナニアは、石の壁にもたれながら耳を傾けた。東から起こされる者。それは、ペルシャの王キュロスのことか。あるいは、もっと深遠な、目に見えぬ御手の動きを示すものか。預言の言葉は、単なる未来の予告ではない。それは、今、ここにいる者たちの現実を、全く異なる光で照らし出す窓のようなものだ。
読まれる言葉は続く。「『しかし、わたしの僕であるイスラエル、わたしの選んだヤコブよ、恐れるな。…あなたを強くするために、わたしはあなたを助ける。わたしの義の右の手をもって、あなたをささえるからだ。』」
「恐れるな。」 その短い言葉が、広場に立ち込めていた重い空気を、初めて切った。アナニアは、自分の中に巣くっていた「恐れ」が、名前を持った実体であることに、その時気づいた。それは国々の騒ぎでも、剣の輝きでもなく、ただ「わたしはあなたと共にいる」という約束が消え去ってしまうことへの恐れだった。彼は、掌の中の陶器の欠片を握りしめた。それはただの破片ではない。かつてそれは、全体の中にあって、確かな用を為していたのだ。
夕暮れが近づき、影が長く伸び始めた。人々はそれぞれに、複雑な表情を浮かべて立ち去っていった。アナニアは最後までそこに残り、荒れ野に沈んでいく太陽を見つめた。預言の言葉は、現状を楽観させるような安易な慰めではなかった。むしろ、嵐のような現実を直視させた上で、その嵐の只中に、揺るがない岩があることを告げるものだった。
彼は家路についた。道端には、いばらが茂っていた。そのいばらの中に、一輪の赤い野の花が咲いているのに気づいた。それは、誰の目にも留まらないような、取るに足らない小さな命だった。しかし、そこにあった。アナニアは立ち止まった。神の言葉は、陶器の欠片のように、この花のように、一見無力で、取るに足らないものの中に、その約告を隠しているのではないか。選びとは、強大さによるのではない。この、干上がった土地で、ほんのわずかな露にすがって咲く花のような、その在り方そのものに、意味があるのだと。
家の戸口に着くと、彼は部屋の奥から、埃をかぶった小さな木箱を取り出した。中には、父から受け継いだ、古びた契約の言葉が記された皮の切れ端がしまってある。彼はそれを広げた。直接イザヤの新しい言葉は記されていない。しかし、そこにある古い約束は、今日聞いた言葉と全く同じ息吹を持っていた。
「東から人を起こすお方よ。」 アナニアは窓の外の闇に向かって、声にならない祈りをささげた。「この弱り果てた者を、あなたの僕として見出してくださるなら。この震える手をもって、何を為せというのでしょう。」
返答はなかった。しかし、彼の中に、確かな変化が起こっていた。恐れは消えなかったが、その恐れを包み込む、より大きな確信が、静かに心の奥底から湧き上がってくるのを感じた。それは、嵐の中にある岩の感触だった。
彼は翌日、再び村の広場に現れた。顔を上げ、背筋を伸ばして。何も変わってはいない。バビロンの影は相変わらず濃い。しかし、アナニアはエリアキムや他の若者たちに、自ら語りかけた。陶器の欠片を見せながら。
「これは壺の一部だ。今は無用のものに見える。しかし、かつては清い水を満たし、渇きを癒した。我々も同じだ。今は散らされ、砕かれたように見える。しかし、我々は、ある『全体』の、欠くべからざる一部なのだ。東から西から、神はご自身の目的のために人を起こされる。その御手の内にあって、一粒の麦も、一片の陶器も、無意味ではない。」
彼の言葉は雄弁でも力強いものでもなかった。時には詰まり、言い淀みもした。しかし、そこには、昨日までにはなかった、地に足のついた確かさがあった。それは、イザヤの言葉が単に耳を通り過ぎたのではなく、この年老いた男の骨と肉の中に、根を下ろし始めた証だった。
日々は相変わらず厳しかった。しかし、アナニアの祈りは変わった。それは、救いを求める叫びから、静かな信頼の内に沈黙する時間へと移り変わっていった。彼は、荒れ野を見つめながら、その野原がいつか喜びと感謝をもって主を誉め歌う日が来ることを、目を凝らして見ようとした。見えるものは、相変わらずの乾きと、いばらだけだった。だが、彼の心の耳には、もう一つの声が聞こえていた。それは、「恐れるな、わたしはあなたと共にいる」という、繰り返される、消えることのない旋律だった。
そして彼は気づいた。真の物語とは、東から起こされる偉大な王の武勇伝などではない。むしろ、一片の陶器が、壺としての本来の用を見出し、再び清い水を満たすその時まで、乾いた土の中で、静かに待ち続けることなのだと。預言は、その待ち望みに、確かな名前を与える。その名は、「共にいます神」という名であった。