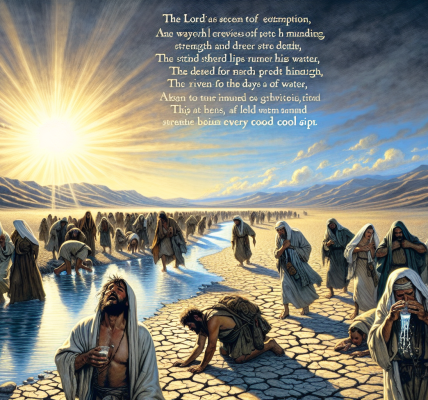ダリウス王の治世二年、秋の気配がユーフラテス川の西に広がる州を覆い始めた頃、ゼカリヤという名の若い祭司は、エルサレムの廃墟にたたずんでいた。彼の父祖の名はベルキヤ、その父はイドといい、捕囚の民の中にあって主の言葉を忘れまいとする一族の出だった。風が砕けた石の間を吹き抜け、かつて栄華を誇った町の残骸に土埃を舞い上げる。ゼカリヤはその風に衣を翻しながら、目を閉じた。心の中には、遠いバビロンで聴いた古老たちの声、神殿の喪失と約束の地への帰還という、重く矛盾した記憶が絡み合っていた。
ある夜、彼が仮住まいの家で羊皮紙を巻き戻していると、額に冷たい感覚が走った。ろうそくの炎がゆらめき、壁の影が踊る。それは十一月、シェバットの月のことであった。彼は突然、眠気に襲われ、机にうつ伏せになった。夢か、現か。そこには、びゃくたんの木立が茂る谷間が見えた。木々の間は深い影に沈んでいたが、その下に、三騎、いや四騎とも数えきれぬ馬が立ち並んでいる。毛並みはそれぞれに異なり、一頭は燃えるような栗毛、一匹は深い夜のように黒く、もう一頭は雪のように白かった。鞍には男たちが座し、彼らの背筋は緊張に張り詰めているようでありながら、どこか静謐にも見えた。
「主はお尋ねになる」と、ひとりの声がゼカリヤの脳裏に直接響いた。それは彼の背後に立つ御使いの声だと、なぜか悟った。「我々は地を行き巡り、見て参りました。見よ、全地は平穏に座している」
平穏。その言葉がゼカリヤの胸を締め付けた。エルサレムは石塚に過ぎず、帰還した民は貧窮と敵対する周囲の民の嘲笑に喘いでいる。これが平穏なのか。彼の内から、疑問がほとばしった。すると、先の御使いが主に向かって言う声が聞こえた。「万軍の主よ、あなたはエルサレムとユダの町々を、七十年の間お怒りになってきました。いつまで、あなたはこれを憐れまれないのですか」
その問いの後、一瞬の沈黙が空気を満たした。びゃくたんの葉も揺るがぬ静けさ。そして主が、優しく、しかし揺るぎない言葉で答えた。「私は、エルサレムを、シオンを、激しい情熱をもって愛している。私が僅かな怒りをもって臨んだあの国々は、逆に災いを加え、悪をなした。それゆえ、私は今、エルサレムに帰り、私の家がその中に建てられることを望む。測り縄がエルサレムに張り巡らされるであろう」
主の声はさらに続いた。「叫べ。万軍の主はこう言われる。私はエルサレムを、シオンを、嫉むほどに慕っている。私は安らかな町々に怒りをもって臨む。私が僅かに怒ったとき、彼らは破壊を助長したからだ。しかし、主はふたたびシオンを慰め、エルサレムを選ぶ」
ゼカリヤはその言葉を、夢の中の夢のように受け止めた。目が覚めると、枕元には夜明けの淡い光が差し込み、頬には涙が伝っていた。彼は起き上がり、戸外に出た。東の空が葡萄色から茜色へと変わりつつある。彼は主の言葉を胸に刻み、人々に語り始めねばならなかった。かつての預言者たちの警告を思い出せ、と。主の道に立ち帰れ、と。彼らは去り、災いに遭った。しかし、主の言葉は立ち続ける、と。
それから数日後、再び異象が彼を訪れた。今度は、鍛冶屋の工房のような場所だった。あるいは野原かもしれない。そこに、四本の巨大な角がそびえ立っていた。それは恐ろしいほどの威圧感で、四方八方に向かって突き出ており、ユダ、イスラエル、エルサレムを散らし、押しのけ、もう誰も頭をもたげることができないように思わせた。ゼカリヤはその光景に息を呑んだ。角は圧政の象徴か、あるいは散らす者たちそのものか。
「これらは何ですか」と彼は傍らに立つ御使いに尋ねた。
御使いは少し間を置いてから答えた。「これらは、ユダを散らして彼らに顔を上げさせなかった角だ」その声には、嘲りにも似た冷たさがあった。
すると、突然、四人の男たちが現れた。彼らは工匠、あるいは鍛冶職人の風体で、手には工具を握っている。ゼカリヤは彼らが何をするのかを見た。工匠たちは四本の角に向かって歩み寄り、一つ一つを打ち、投げ倒し始めたのだ。角は恐怖の象徴としてそびえていたが、工匠たちの手にかかると、陶器のように砕け散った。その動作は乱暴というよりも、ある必然に従った儀式のようだった。
「彼らは何をするのですか」ゼカリヤは再び尋ねた。
御使いは言った。「これらの角がユダを散らし、人に頭を上げさせなかった。それゆえ、これらの工匠は来て、角をおののかせ、かつてユダの地に向かって角を振るった国々を打ち倒すためだ」
幻はゆっくりと薄れていった。ゼカリヤは工房の残像のような光と影のなかに立ち尽くしていた。外では、エルサレム再建のための石切りの音が、規則的ではなく、時折途切れながら響いている。彼はその音を聴きながら、ふと理解した。主の怒りは真実だが、主のあわれみもまた真実であると。四本の角は確かに現実の脅威だった。ペルシャ帝国の支配下でさえ、周囲のサマリヤやアンモンその他からの敵意は消えていない。しかし、四人の工匠もまた、主が備えられる救いの手段なのだ。
彼は羊皮紙を取り、葦の筆にインクを浸した。震える手で、彼が見たこと、聞いたことを記し始めた。「ダリウス王の二年、シェバットの月の二十四日に…」書き進めるうちに、彼の心には確信が漲ってきた。荒廃は終わる。測り縄が張られ、神殿の礎石が据えられる日が来る。主の嫉みとも言えるほどの愛が、この場所を再び聖なるものとする。
ゼカリヤは書き終えると、戸外に出て、遠くに見える工事現場を見つめた。埃の中で働く人々の姿は小さく見えたが、彼らの背中には、幻に現れた工匠たちと同じ確かなる何かが宿っているように思えた。風が変わった。もう秋の終わりを告げる冷たさではなく、どこか春の兆しを運ぶ柔らかさを含んでいた。主の言葉は、石の隙間からも、疲れた民の嘆きからも、決して離れることはない。彼はそれを、骨の髄まで感じ取った。そして、新しい一日が始まろうとしているのを、静かに待った。