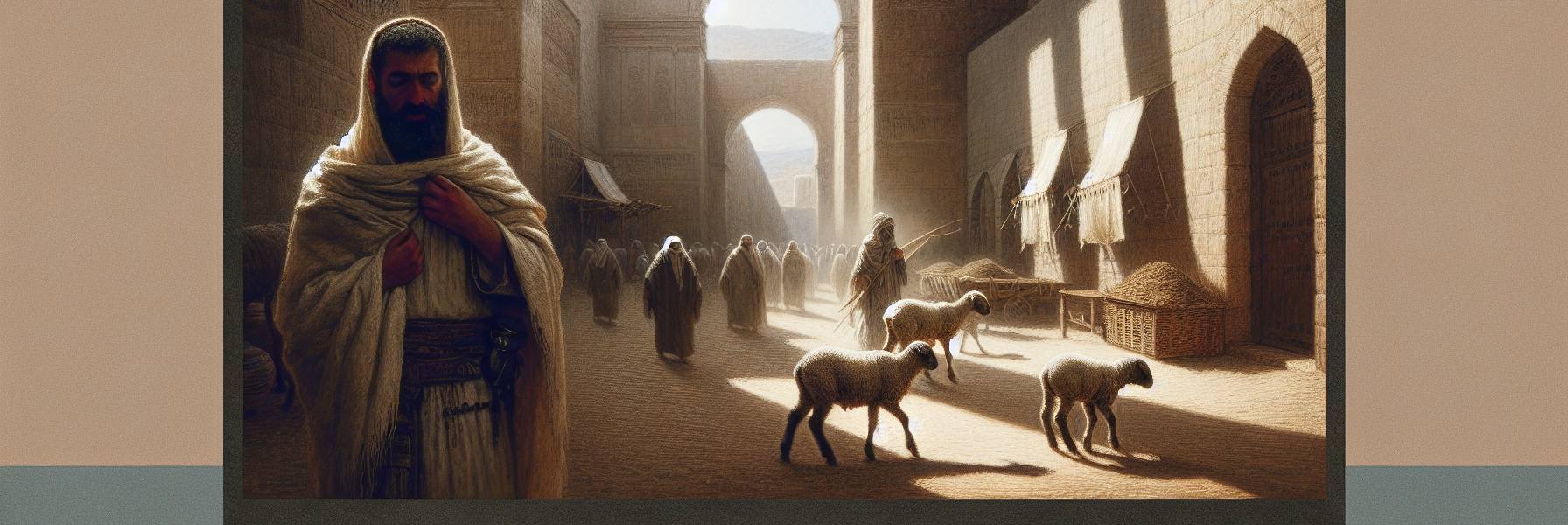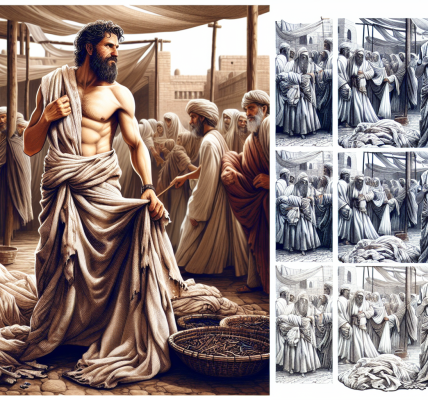朝もやが幕屋の周りの野営地を覆っていた。砂漠の冷たい空気が、ほんのりと煙の気配を運んでくる。アヒムは柵の中で一番無傷な雄羊を選び、その首に荒い縄をかけた。羊は抵抗もせず、ただ琥珀色の瞳で彼を見つめた。その目に映る自分の姿が、何故か胸を締め付ける。
レビの子孫である祭司エルアザルは、すでに祭壇の前で火を整えていた。彼の腕は、幾度も同じ動作を繰り返してきたため、無駄のない動きを覚えている。アヒムが羊を引いて近づくと、エルアザルはうなずいただけだ。言葉は要らない。この場所では、全てが沈黙と所作で成り立っていた。
「主の御前で」とエルアザルが低く言った。その声は乾いた風のように渇いていた。アヒムは羊を幕屋の入り口、つまり会見の天幕の前に連れて行った。彼自身の手で。これが定めだ。彼は羊の頭に両手を置く。手の下で、生き物の温もりが脈打っている。自分の罪、家族の汚れ、知らずに犯した過ち──全てをこの生き物の上に移すような気持ちで、重く押す。羊は静かに一声鳴いた。その鳴き声が、アヒムの胸の奥で何かを引き裂くようだった。
屠る時、彼の手は震えなかった。むしろ、あまりに冷静な自分が怖くなった。銀色に光る刃物が喉元を通り、赤い生命が土に滴る。エルアザルがすぐに青銅の鉢を受けさせた。血は貴重だ。無造作に流されるものではない。祭司はその血を執拗に、祭壇の基の四方に注いでいく。滴る音だけが、砂に吸い込まれる。血は土に帰るのではなく、聖なるものとして祭壇と一つになる。その手順一つ一つに、意味があるのだとアヒムは思う。意味が分からなくても、従うこと自体が言葉にならない祈りなのだ。
次は皮を剥ぐ。エルアザルの手際は早い。しかし、乱暴ではない。むしろ尊厳をもって扱っている。剥がされた皮は傍らに置かれ、肉は水で洗われる。特に内臓と腿は、砂漠の塵を洗い流すために、丁寧に清められた。水の音が、不意にこの厳粛な空間に生気をもたらす。洗われた肉は、一つ一つ祭壇の上に並べられる。頭、脂肪、内臓…全てだ。残すものは何もない。これが全焼の犠牲、燔祭なのだ。
エルアザルが火種を近づける時、アヒムは息を詰めた。最初はぱちぱちという小さな音だった。脂肪が熱に反応し、炎が青からオレンジへと変わる。そして煙が立ち上る。真っ直ぐに、ゆっくりと。朝もやの中を貫いて天へ向かうその煙は、もはや単なる煙ではなかった。アヒムは旧く父から聞いた言葉を思い出す。「宥めの香り」──主への香ばしい匂い。焼ける肉の匂いは、確かに食欲をそそるものではなかった。むしろ、少し焦げる匂いが混じる。しかし、その煙が象徴するものは、彼のささげた全て、彼自身の悔い改めの全てだった。
炎はやがて全てを包み、祭壇の上の供え物を灰へと変えていった。エルアザルは灰を集め、清い場所に運ぶために準備を始める。アヒムはまだその場に立ち尽くしていた。手には羊の縄を持った感触が残っている。そして胸には、得体の知れない安堵のような、喪失のようなものが広がっていた。罪が贖われたという確信よりも、まずは「従った」という事実が、彼を空っぽにさせた。
ふと、エルアザルが彼の方を見て、わずかに頷いた。老人の目には、同じ光景を何百回と見てきた諦めではなく、今日という日の儀式だけを見つめる新鮮な静けさがあった。アヒムは礼を言おうとしたが、言葉が出ない。代わりに深く頭を下げた。
帰路、野営地には生活の音が聞こえ始めていた。子供の声、鍋の音。平穏な日常。彼がさっきまでいた場所の厳粛さが、嘘のようだ。しかし彼の鼻には、まだあの煙の匂いがくすぶっていた。それはもはや焦げた匂いではなく、何か清められたような、鋭い香りとして記憶に刻まれる。
家の入り口で妻が出迎えた。彼女は何も尋ねない。彼の顔を見て、小さく息をついただけだ。アヒムはようやく言葉を見つけた。「終わった」ただそれだけ。妻はうなずき、手に持っていた水の皮袋を渡した。彼が水を飲む間、彼女は遠くの幕屋から今も細く立ち上る煙を見つめていた。
アヒムは思う。あの雄羊は彼の代わりになったのか。いや、そう単純ではないのかもしれない。血と火と煙──それら全てが複雑に絡み合い、見えざる契約を更新する。今日という日が、また明日の罪を許すわけではない。それでも、灰になった羊のように、彼自身の傲慢さもまた焼き尽くされる必要があった。儀式は、外側の清めだけでなく、内側の順服を形作るためのものなのだ。
夕暮れが近づき、幕屋の祭壇の火は消えないように整えられる。アヒムは再び遠くからそれを眺めた。一点の炎が、闇が迫る荒野で揺らいでいる。彼は、それがただの火ではなく、民全体の祈り、罪、希望が絶えずささげられている場所だと理解した。レビ記の言葉は、石板に刻まれた冷たい律法ではない。血の温もりと、煙の行方と、灰の積もりの中で、生きて呼吸する神との交わりの道筋なのだ。
彼はそっと胸に手を当てた。そこには、何か重いものがあった。けれども、朝とは違って、それはもう彼だけの重さではなかった。燔祭の煙と共に、いくらかは天に運ばれたような、そんな気がしてならなかった。明日もまた罪を犯すかもしれない。それでも、またあの場所に立つことはできる。彼はそう信じるために、今日の羊と炎と灰を、心に刻みつけたのだった。