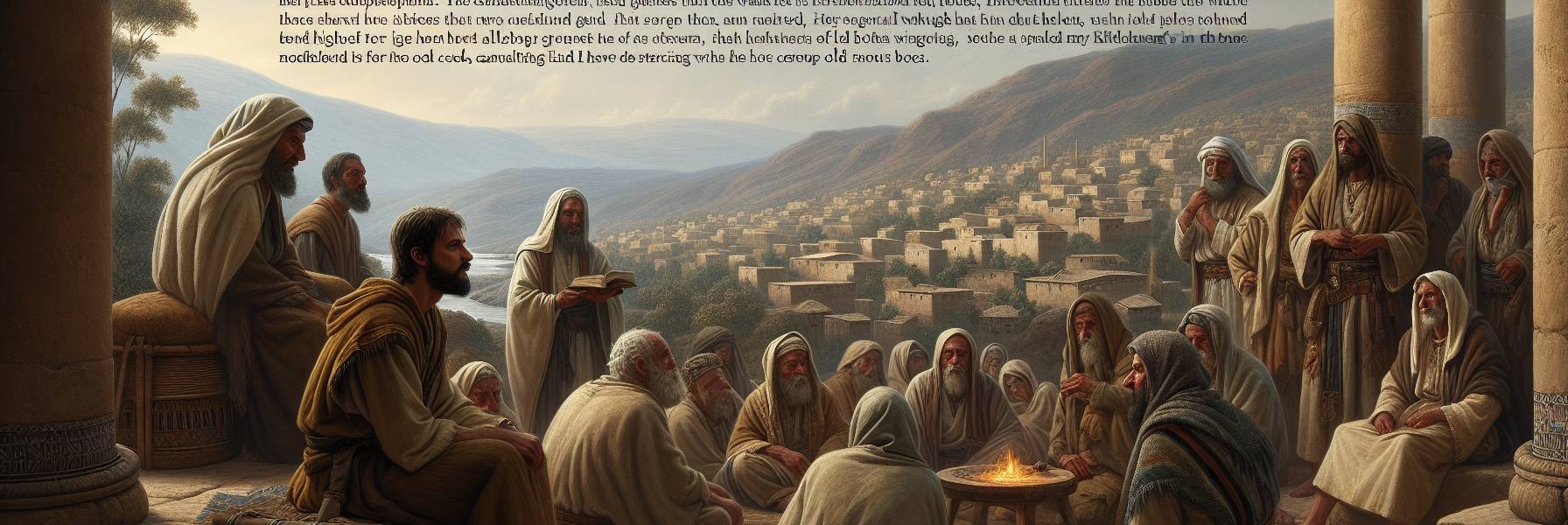ヨルダン川の東、風が乾いた土を巻き上げる高原で、預言者エゼキエルの言葉は、石のように重く、鋭く響いた。彼はバビロンの河の畔に座していたが、その心の目ははるか離れた同胞の地、エルサレムの崩壊を見つめていた。その破壊を、周囲の民は冷笑と共に見ていた。
アンモンの地では、祭司たちがモレクの像の前で煙を立てていた。羊の革のテントからは、油と香料の匂いが漂う。首長たちが葡萄酒を酌み交わす天幕の中で、一人の使者が駆け込んだ。エルサレムの石が一つ残らず崩され、ユダの民が捕らわれの身となった、と。たちまち、ざわめきが広がった。ある者は杯を掲げ、ある者は哄笑を漏らした。「ついにあの高ぶる者どもが倒された!」「主の聖所? 砂の城に過ぎなかったのだ!」その喜びは、神殿の庭を血で汚した者たちへの憎悪から湧き上がるものではなかった。むしろ、ただ隣人の不幸を、自らの幸運の糧としようとする、浅はかで醜い歓びだった。それは、親族の苦難を前にして手を揉む者の笑みである。アンモンは、イスラエルがついに力を失い、荒れ野のごとくになったことを、自らの利益の始まりと確信した。しかし、その確信はやがて砂漠の蜃気楼のように消え去ることを、彼らは知らなかった。東から来る荒ぶる民が、彼らの城壁を粉砕し、彼らの地を駱駝の放牧場とし、やがて自らも歴史の風に散る運命にあることを。
南へ下れば、モアブの岩だらけの丘陵が続く。死海の塩の気配が風に乗ってくる。彼らはこう言い交わした。「見よ、ユダの家も、他のすべての国々と変わることないではないか。」その言葉には、軽蔑がにじんでいた。選ばれた民という特別な地位、主との契約――それを、長い年月、隣国は歯がゆさと共に見てきた。そして今、その契約が空しい夢に終わったと確信したとき、彼らは安心し、嘲笑した。神々の国と人の国との違いなどない、すべては力と運にすぎない、と。しかし、その嘲りは、自らに向けられる刃ともなる。彼らが否定した「違い」は、実は裁きの厳しさにおける違いとして立ち現れる。主は、セイルの丘から始まる戦いの叫びをもって、モアブの要害を崩される。美しい都市は荒廃し、かつての栄光は、ただ「ここにモアブがあった」という噂に変わる。
海岸の平野に目を転じれば、ペリシテのガザとアシュケロンは、古くからの憎しみを胸に、ユダの破滅に復讐の機会を見出していた。彼らは、執念深く、心に留めておく民である。昔の傷は癒えず、ただ機会をうかがっていた。ついにその時が来た。彼らは手をこすり、武器を研ぎ澄ませた。弱った者をさらに痛めつけ、永遠に絶やさんとした。その憎悪は、理性を超え、破滅への狂奔となった。しかし、主は言われる。手を上げる者には、必ずその手を折る方がおられると。北からの破壊者が、ペリシテの海岸を血に染め、その誇りであった海の交易の町を、沈黙する漁村に変える。主の激しい怒りが、彼らの上に下る。それは、彼らが隣人に与えようとした絶滅そのものだ。
そして、南東の険しい山岳地帯、セイルの山に住むエドム。彼らは血縁でありながら、最も冷酷に振る舞った。イスラエルが災いに遭った時、エドムは手を下した。逃げ惑う者を剣で討ち、生き残った者を敵に引き渡し、自分たちも掠奪に加わった。兄弟の苦しみを、自らの利益へと変える機会と捉えたのだ。「彼らは我々のものだ」とばかりに。その行為は、単なる敵意を超え、裏切りであり、自然の情に背くものだった。主は、彼らの山々にわたし自身の手を向ける、と言われる。人も獣も絶やし、荒廃から荒廃へと変える。彼らがイスラエルの家に行ったことを、そのまま彼らの上に返される。彼らは、主を知る――主こそが裁きを行われる方であることを、その地にひれ伏して知るのである。
エゼキエルは、これらの言葉を語り終えても、顔は石のように硬かった。彼の胸中には、複雑な思いが渦巻いていた。同胞の罪の結果としての裁きは厳しいが、周囲の民の嘲りと悪意に対する主の憤りもまた、圧倒的に重い。主は、ご自身の聖なる名がけがされることを許されない。異邦の民が「彼らの神は弱い」と蔑む時、主はご自身の力を示される。それは救いのためではなく、審判のためとして。
風がバビロンの河の水を揺らし、柳の葉がさらさらと音を立てた。遠い地での破滅と、遠い未来での回復を、この預言者は同時に見ていた。今は裁きの時。主の手は重く、その御声は雷のごとく諸国に響く。そして、その響きが消えた後、深い沈黙だけが残る。それは、全ての民が、主こそが神であることを知る日の前の、厳粛な間合いに似ていた。