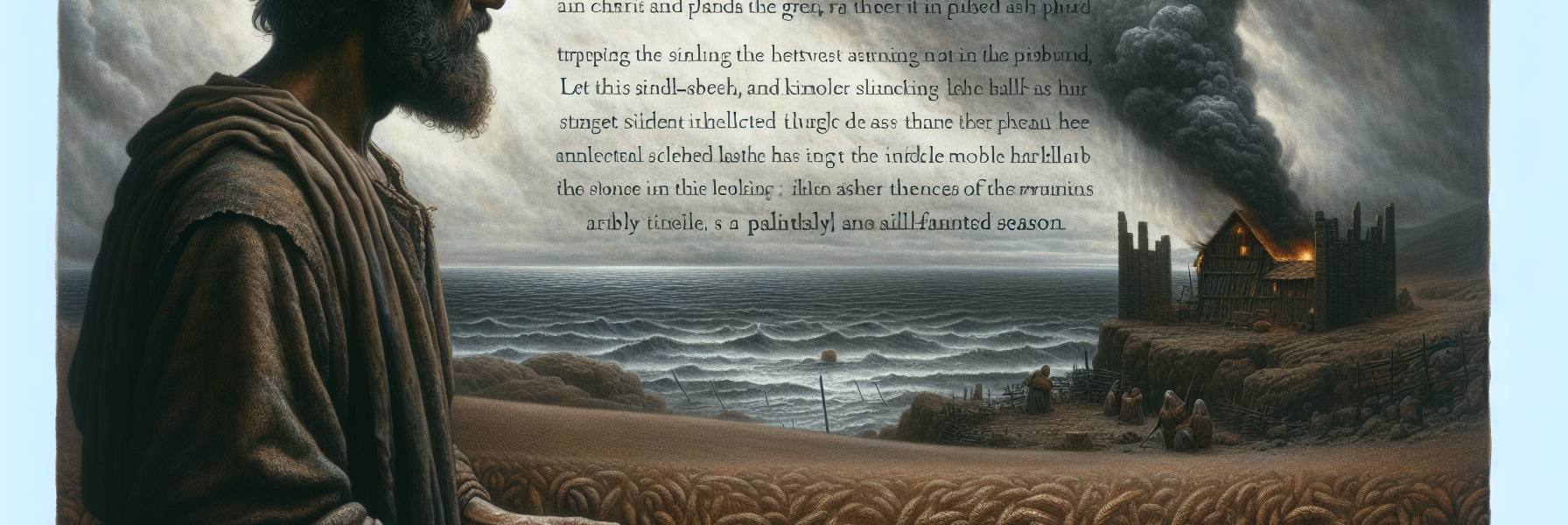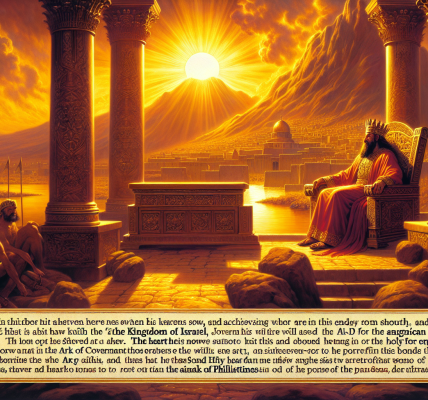その日も海は鉛色をしていた。潮風が渦巻く長崎の岬の村で、ヨシオは荒れた畑を耕していた。鍬の柄には手のひらに馴染んだ窪みができており、振り下ろすたびに鈍い音を立てて乾いた土を裂く。もう何日も雨は降っていない。妻を病で失ってから、ことばそのものが喉の奥で砂のように澱んでいた。教会へ行く気力も、祈る言葉も、すべてが灰のように散っていた。
夕暮れ時、漁から帰る船団のざわめきが風に乗ってくる。彼は鍬を置き、額の汗を腕で拭った。すると、村の小道を、よぼよぼと歩いてくる影が見えた。ソウゾウじいさんであった。村で最も年をとった男で、誰もがその過去を詳しく知る者は少なかったが、どこか深い落ち着きを湛えていた。
「ヨシオよ、腰を降ろせ。この石が冷たいわけでもない」
じいさんは岬の見える大きな岩に腰を下ろし、煙管をくゆらせた。ヨシオは黙って隣に座った。目の前には、太陽に照らされて金色に波立つ海が広がっていたが、彼の心にはただ荒涼とした海原が横たわっているだけだった。
「この海はな、穏やかで美しいように見えるが、底ではいつも暗い渦が巻いている。それが海というものだ」
ソウゾウじいさんはゆっくりと話し始めた。声は潮風にさらされてかすれていた。
「お前の心の中にも、今、大きな渦が巻いている。それは仕方のないことだ。試練に遭うときは、だれでもそうなる」
じいさんは煙管を揺すり、灰を落とした。
「だがな、その渦の中にこそ、何かが育つ土壌がある。忍耐というものが。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、お前は何一つ欠けたところのない、全き者とされるのだ」
ヨシオはじいさんの横顔を見た。深い皺が刻まれたその顔は、何十年もの風と塩害に耐えてきた岬の岩のようだった。彼は何も言わなかった。言葉がまだ見つからなかった。
「わたしは、昔、遠い国からこの地に、ある書を携えてきた」
突然、じいさんが低声で言った。周りに誰もいないのを確かめるように目を走らせて。
「そこに書かれていた言葉を、今でも忘れぬ。『あなたがたのうちに知恵に欠けているものがあるなら、…神に願いなさい。そうすれば、…すべての人に惜しみなく、とがめだてしないでお与えになる神から、与えられるでしょう』」
「知恵など、今の私に何になるでしょうか」
ヨシオは初めて口を開き、自分の声の乾ききった響きに驚いた。
「畑はカラカラで、空は雨を忘れ、私は…私は祈ることさえできません」
「ふむ」
じいさんはうなるように唸った。
「では、こう聞こう。お前が神に願っているのは、雨か? それとも、この乾きの中でも揺るがない何かか?」
彼の目は、遠くの水平線に固定された。
「疑いながら願う者は、風に吹かれて揺れ動く海の波のようだ。あの波を見よ。きょうは西から、あすは東から。そんな者は、主から何かをいただけると思ってはならない。心が二つに定まらない者だからだ」
その言葉は、ヨシオの胸にずしりと響いた。確かに彼は、祈るときも、祈りが天に届くかどうか、半信半疑だった。むしろ、届かないことを恐れていた。
数日後、ヨシオは思い切って、村から少し離れた山中の小さな隠れ家のような場所へ向かった。ソウゾウじいさんがそっと教えてくれた場所だった。そこには、わずか数人の人々がひっそりと集まり、声を潜めて祈り、古びた一冊の書物を読み合っていた。彼らは「書」を「ヤコブの手紙」と呼んでいた。
暗い室内で、ランプの灯だけがゆらめいていた。読まれる言葉は、じいさんが語ったものと重なった。
「…人は誘惑に会うとき、自分は神に誘惑されている、と言ってはならない。神は…悪の誘惑に会われることはなく、またご自分で人を誘惑することもない」
読んでいた男が顔を上げ、静かに言った。
「私たちの内なる欲望が、私たちを引き寄せ、捕らえるのです。そして、欲望がはらめば罪を生み、罪が熟すれば死を生みます」
ヨシオは自分の中に渦巻いていた感情の正体を、初めてはっきり見たような気がした。妻を失った悲しみ以上に、神への怒り、なぜ彼女を奪ったのかという不信、全てを投げ出したいという無力感。それらが、荒れ野のように心を占めていた。
月日は流れた。雨は依然として降らず、畑の作物はやせ細った。しかし、ヨシオは毎週、その山中の集まりに足を運ぶようになった。彼は多くを語らなかったが、耳を傾けた。そして、ある晴れた午後、彼は荒れた畑の端で一人、つぶやくように祈った。立派な言葉ではなかった。ただ、「この乾きの中でも、あなたを信じる力をください」という、短い、切ない願いだけだった。
その夜、久しぶりに妻の夢を見た。彼女は何も言わず、ただ静かに笑っている。目が覚めると、枕は涙で濡れていたが、心は前のような荒涼とした感じではなかった。一種の静けさ、まるで嵐の後の海が一時的に凪いだような、深い静寂があった。
次の集まりで、ヨシオは少しばかり自分の思いを口にした。言葉はたどたどしく、時につかえた。すると、集まりの最も年老いた婦人が、にっこりと笑って言った。
「聞きなさい、愛する兄弟たち。神はみこころのままに、真理のことばをもって私たちをお生みになりました。それは、私たちが、いわば被造物の初穂となるためなのです」
彼女は膝の上に置かれたヤコブの手紙をそっと撫でながら続けた。
「ですから、すべての人は、聞くには早く、語るにはおそく、怒るにはおそくあるべきです。人の怒りは、神の義を実現しないのですから」
怒るにはおそく。ヨシオはその言葉を反芻した。彼は長い間、神に対して、運命に対して、怒りに燃えていた。その怒りが、彼をさらに孤独で乾いた場所に追いやっていたのだ。
秋が深まる頃、ついに長雨が訪れた。畑の土は黒く潤い、かすかに次の命の息吹を感じさせた。ヨシオは雨に打たれながら、荒れ地に佇んだ。すべてが解決したわけではなかった。妻のいない寂しさは、まだ胸の奥に穴を開けていた。しかし、彼はもう、その試練を呪うだけではなかった。なぜなら、その乾きの只中で、彼は自分自身の信仰の脆さと、それでもすがるべきものの存在を、かすかながら知ったからだ。
ソウゾウじいさんが言っていた。「自分を欺く敬虔な人」になってはならない、と。聞くだけで行わない者は、写し鏡に映った自分の顔を見て、そのまま去る者だ。もっと深く見つめ、自由をもたらす完全な律法を心に刻み、それを実行する者になれ、と。
雨が小止みになったとき、ヨシオは家の中の、ほこりを被った小さな祭壇に向かった。そして、そっと十字架を拭い清めた。行動はまだ小さな一歩でしかない。だが、彼はもう、嵐の中をただ漂流する小さな舟ではなかった。たとえ進みが遅くとも、艪を握り、暗い海原に向かって漕ぎ出そうとする、一艘の舟だった。
岬の向こうでは、雨雲の切れ間から弱い陽光が差し、海を銀色に染めていた。すべてが変わったわけではない。しかし、見る目の奥底にある何かが、確かに静かに、ゆっくりと、変化していた。試練は喜ばしいものではない。だが、その忍耐が、荒れ野に一筋の水路を刻み始めることを、ヨシオはまだ言葉にならない感覚として、受け入れ始めていた。