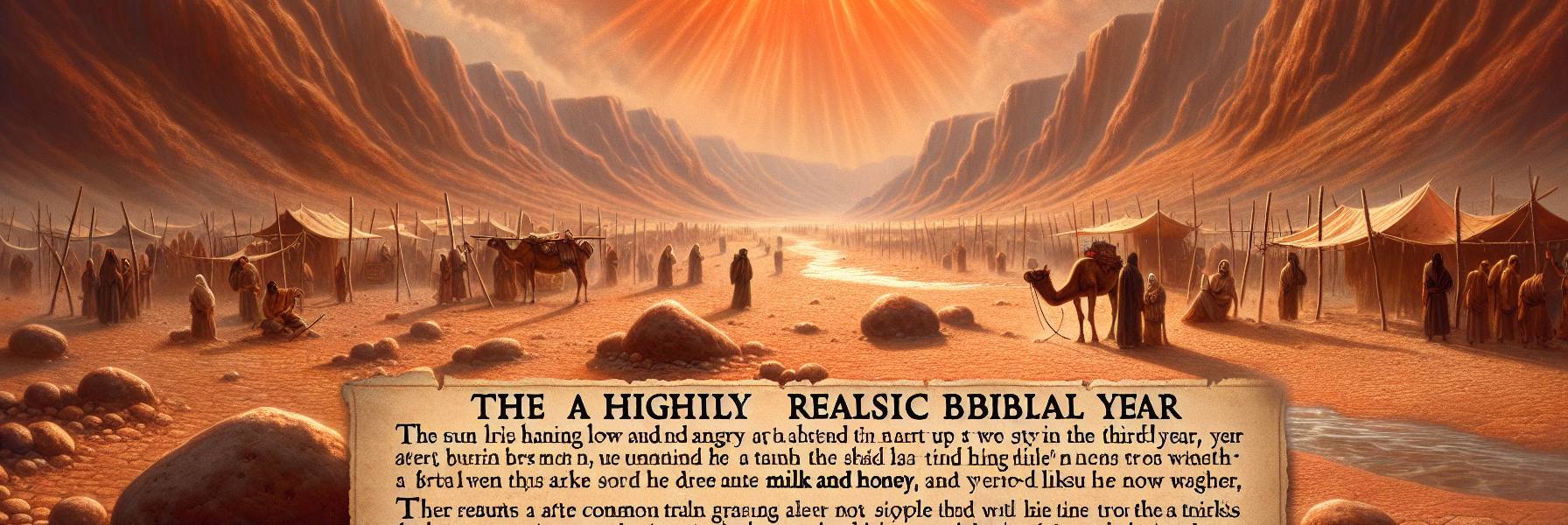夕暮れがギルガルの丘を縁取った頃、エリアフは最後の羊を囲いに入れ、その背中に刻まれた古い傷がうずくのを感じていた。西風がオリーブの木々を通り抜け、砂と乾いた草の匂いを運んでくる。彼はふと、少年の頃、父と共にこの同じ丘で夕焼けを見ながら聞いた言葉を思い出した。「我が子よ、あなたの神、主を愛して歩め。」
村へ下る道すがら、彼は異様な賑わいを耳にした。普段は静かな広場に、松明の灯りが揺れ、人々が集まっている。中心には、長旅から帰還したばかりのマナセの姿があった。幼い頃、共に羊を追った友だちだ。マナセの声は熱を帯び、手にはエジプト風の精巧な小像が握られていた。
「…見よ、友よ。私がアラムの地で目にしたものは、驚きに満ちていた。彼らの神々は即座に恵みを与えてくれる。雨を呼び、産みの苦しみを軽くする。なぜ我々は、いつも試練を与えるだけの神に縛られねばならないのか?」
エリアフの胸に、冷たい石が転がり込んだような感覚が広がった。周りの顔には、疲労と飢えの影が刻まれていた。去年の旱魃がまだ記憶に新しく、今年の春も雨は少なかった。人々の目が、マナセの手にある金色に輝く像へ吸い寄せられていくのが分かる。
その夜、エリアフは家で妻と無言の食事を取った。炉の火が揺らめき、壁に律法の言葉が書かれた羊皮紙の影を落としている。マナセの声が耳から離れない。「約束の地に入れば豊かになると言われたが、現実は石だらけの畑と、飢えた子らの泣き声ではないか。」 そう考えると、心がざわめいた。
三日後、事態は思わぬ方向へ進んだ。マナセは単なる旅行者の話ではなく、「夢を見た」と主張し始めたのだ。「天からの使いたちが、新しい契約を示された。主こそが真の神だが、この地の力を借りることを禁じてはいない、と。」 彼の口調は真摯で、目にはかつてない輝きがあった。村の長老の一人でさえ、「預言者の言葉には耳を傾けるべきではないか」と呟くほどだった。
エリアフは苦しんだ。マナセは嘘つきではない。かつて狼の群れから共に逃げた友だちだ。しかし父の教えは厳格だった。「たとえ預言者が立ち上がり、しるしや奇跡を見せても、あなたがたの知らなかったほかの神々に従えと誘うなら、彼に聞いてはならない。」
苦悩は深まるばかりだった。ある晩、幼い娘が熱を出してうなされた時、エリアフは思わず手を合わせた。その瞬間、ふとマナセの言葉がよみがえり、自分が何をしようとしているのかに気づいて震えが止まらなくなった。彼は夜明けまで娘の傍らに座り、祈り続けた。祈るべき御名が、喉の奥で揺れた。
転機は穏やかな月夜に訪れた。マナセが村全体を招き、広場で「和解の儀式」と称する集いを開いた。彼はエジプトとカナンの神々の小像を並べ、その前で雄羊を屠った。甘い香りの煙が立ち上り、何人かが魅了されたように前に進み出た。エリアフはその時、ある光景を目にした。村の最も敬虔な老女リヴカが、そっと席を立ち、背を向けて去っていく姿だ。彼女の背中はまるで、嵐の中の一本のオリーブの木のように、細く、しかし確固としていた。
その瞬間、エリアフの内なるざわめきが静まった。友への情実、不安、孤独な恐怖ーそれら全てが、ある一点に収束するのを感じた。彼は立ち上がり、声を張り上げたわけではなかった。むしろ、砂を踏む足音が広場のざわめきを次第に消していった。彼はマナセの真ん前に立ち、幼い日々の思い出ー共に食べた無花果、逃げた狼、主に捧げた初めての子羊ーの全てを胸に詰め込み、こう言った。
「我々は既に聞いた。我々の神は唯一だ。あなたの道は、我々を先祖の約束から引き離すものだ。」
沈黙が広がった。マナセの目に一瞬、痛みのようなものが走った。しかし彼は首を振り、「あなたは村を滅ぼすつもりか」と返した。エリアフは答えなかった。彼はゆっくりと村人一人ひとりの顔を見つめた。疲れた顔、迷った顔、それでもどこかで待ち望んでいる顔。そして彼は、律法が命じることを、言葉ではなく、次の行動で示した。
翌朝、エリアフは長老たちの元を訪れ、曖昧さを一切排した話し合いを求めた。彼は申命記の言葉を繰り返さなかった。代わりに、旱魃で割れた土地のことを、飢えで失った子羊のことを、それでも祖父の時代から守られてきた祭りのことを語った。「主の道は、時に茨の道だ。しかしそれは、我々が迷子にならないための道しるべではないのか。」
最終的に村は動いた。エリアフ一人の力ではない。リヴカのような沈黙の信仰を持つ者たち、迷いながらも結局は先祖の契約を選んだ若者たち、皆が少しずつ、確信を持ち始めたのだ。マナセの影響は、ある夜明け、彼自身が村を去ることによって終わりを告げた。去り際、彼はエリアフを一目見たが、何も言わなかった。
それから一週間後、村人たちは広場に集まった。偶像の破片はすべて火で清められ、灰はキデロンの谷に散らされた。誰も勝利を祝わなかった。むしろ、重い静寂があった。エリアフはその灰を見つめながら、これは敵に対する勝利ではなく、自分自身の内に潜む背信の可能性に対する、小さく、しかし確かな一歩なのだと思った。
月日は流れ、雨はその後もすぐには訪れなかった。しかしエリアフは、ある乾いた土の上で、孫が石を一つ拾い上げ、「これは主が造られた石だね」と呟くのを耳にした。彼はその小さな背中に手を置き、ふと、信仰とは煌びやかな奇跡ではなく、砂の中に隠された一粒の真珠のように、見えないところで育まれるものなのだと悟った。そして、あの時あの決断が、単なる規則の遵守ではなく、渇いた地に水脈を見出すような、深い愛の行為の始まりだったことを、静かに感謝した。