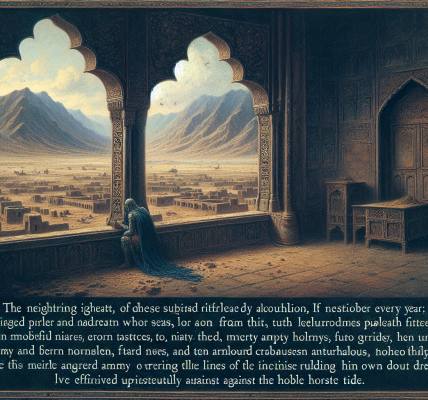夕暮れがぶどう畑の斜面をゆっくりと這い、影を長く引き延ばしていた。一日の仕事を終え、ぶどうの木々の間をそよぐ風が、ほのかな甘い香りを運んでくる。彼は石の壁にもたれ、遠くに見える村の灯りをぼんやりと眺めていた。すると、小道を登ってくる足音が聞こえた。土を踏む音は軽く、確かなリズムを刻んでいる。彼は顔を上げ、目を細めた。
彼女が現れた。肩に空の籠を提げ、顔には少し汗ばんだ輝きがあった。日焼けした足首が、粗い道を歩くたびに砂埃の中に現れ、また隠れる。彼は思わず息を飲んだ。その足の動きは、何か音楽のようなものを感じさせた。かつて見たこともない、研ぎ澄まされた若い雌鹿のそれのようだ。丘の頂きにそびえる岩山の稜線——人々が「ヘルモン」と呼ぶあの山——に群がる子鹿たちの、優雅で危うげな足取りを思い出させた。
「随分と遅かったな」彼は声をかけた。自分の声が、なぜか少し震えているのに気づいた。
彼女は笑った。歯が白く光った。「最後の籠がいっぱいになるまで、待っていたのよ。今年の実は本当に良いみたい」
彼女が近づき、籠を壁際に下ろす。彼は彼女の腿の、ねじれた麻の衣の下にうっすらと浮かぶ力強い曲線を見つめていた。職人による、磨き上げられた象牙の彫刻。円熟した工匠が、一点の曇りもなく仕上げた、滑らかで温もりある作品のようだ。その腿は、大地を踏みしめ、籠を運び、確固として生きることを物語っていた。
「何を見ているの?」彼女は気づき、首をかしげた。その動きで、首筋の髪が揺れた。
「いや……ただ」彼は言葉を探した。「お前が歩いてくるのを見ていて、思ったんだ。お前の足元は、王子の娘のように美しい。いや、王子の娘以上だ。靴ひもも、宝石もいらない。そのままで十分すぎる」
彼女は照れくさそうにうつむいた。彼は彼女のうつむく首筋、そして胸元へと視線を滑らせた。浅く刻まれたへそ——それは満ち足りた酒杯のようだ。決して溢れることのない、熟したぶどう酒が注がれているのだ。彼の目はさらに下へ、そして再び上へと向かった。腹はゆるやかな丘で、ゆりが咲き乱れる野原。豊かさと柔和さをたたえている。
そして、彼女の胸——それは二頭の子鹿、ふたつの双子の羚羊のようだ。柔らかく、温かく、命の鼓動を感じさせる。彼はため息をついた。それは、ため息というよりも、深い祈りのような吐息だった。
「お前の首は象牙のやぐらだ」彼は呟くように言った。「目はヘシュボンの池、バテ・ラバイムの門の傍らに輝く池のようだ。その輝きで、わたしはいつも捕えられてしまう」
彼女は少し離れ、夕日に照らされた彼女の横顔が金色に縁取られた。鼻はダマスコを見下ろすレバノンのやぐらのようにまっすぐで気高い。頭はカルメル山のようだ。髪は深い紫がかった黒、王の従者たちを翻弄する豊かな流れだ。
「そんなふうに言われると、どこか遠くの、触れられないものみたいだわ」彼女は言い、振り返って彼を見た。その目は確かに池のようで、底知れぬ深さを持っていた。
「違う」彼は即座に答えた。「お前はもっと近い。圧倒的に近い。お前のそばに立つとき、わたしは高い椰子の木によじ登り、その実をつかもうとする男のようになる。お前の胸房は、ぶどうの房のように甘く、お前の息のかおりは、最上の林檎のようだ」
彼は一歩近づいた。二人の間に漂う空気が、突然、重くなったように感じられた。
「そしてお前の口は……ああ……」彼は言葉を失った。彼女の口元がほほえんでいる。それは熟したざくろが割れた瞬間の、鮮やかで甘ずっぱい断面を思わせた。彼の頭の中では、言葉が溢れ出した。「お前の口づけは、まさに最上のぶどう酒のようだ。滑らかに、ためらうことなく、わたしの魂の深くへと流れていく。眠っている者の唇でさえ、それを受けて動き出すほどだ」
沈黙が訪れた。ぶどう畑の向こうで、羊飼いの笛の音がかすかに聞こえる。彼女はゆっくりと手を伸ばし、彼の頬に触れた。その手は柔らかく、野のゆりから滴る露のようだった。
「さあ、行きましょう」彼女は囁いた。「野に出て、村里に泊まりましょう。早く起きて、ぶどう畑へ行きましょう。ぶどうの木に花が咲いたか、ざくろのつぼみが開いたかを見に。そこで、わたしはわたしの愛をあなたに与えましょう」
彼は彼女の手を握り返した。その手のひらには、一日の労働の痕が刻まれていたが、それは彼にとって何よりも美しい模様だった。彼女は単なる比喩以上の存在だった。彼女の足は現実の土を踏み、その腿は確かな重量を持ち、そのへそは命の中心を表し、その胸は温もりに満ちていた。彼女は、このぶどう畑と丘と村の、息づく一部だった。そして彼は、このすべてを、まるで初めて見るかのように愛おしいと感じた。
「お前は高い木のようだ」彼はもう一度言った。「高い椰子の木。お前の乳房はその実だ。わたしは言おう、この木によじ登ろう、その枝をつかもう、と。するとお前の乳房は、ぶどうの房のようになり、お前の鼻の香りは林檎のようになる」
彼女は笑い声をあげた。それは鈴を鳴らすような音だった。「そうして、あなたの口には最上のぶどう酒がある。わたしの愛しい人にとって、それはなめらかに流れ、眠っている者の唇さえも、それにこたえて動く」
彼らは肩を並べて小道を下り始めた。影は完全に伸びきり、最初の星が東の空にちらりと光った。彼は彼女の言葉を反芻していた。眠っている者の唇——彼は確かに長い間、何かから眠っていたのかもしれない。単調な日々、意味のない習慣の繰り返しの中に。そして彼女が現れ、彼女というぶどう酒が、彼の内側で静かに発酵し、目覚めをもたらした。
村の灯りが近づくにつれ、家々の輪郭が浮かび上がってきた。彼は彼女の手を強く握った。この愛は、このぶどう畑と同じくらい現実的で、この大地と同じくらい確かなものだった。それは比喩や謎めいた詩句のためではなく、彼女の汗の香りや、足元にまとわりつく土の感触、夕暮れの中で交わされる何気ない会話のために与えられた贈り物だ。
「明日は早いよ」彼が言うと、彼女はうなずいた。
「ええ、分かっているわ。でも今は……ただこのまま歩いていたい」
彼らは沈黙して歩き続けた。道端に咲く野のゆりが、最後の光を浴びて白く浮かび上がっている。彼は彼女を見つめ、心の中で繰り返した。わたしの愛する人、あなたはすべてが美しい。少しの欠けところもない。
そしてそれは、単なる恋人たちの言葉ではなく、この世界の、この生活の、すべての営みへの深い肯定のように思われた。ぶどうの実る季節、揺れるゆりの野、日々を支える労働、そして巡り合う二つの魂——それらすべてが、この夕暮れの小道の上で、ひとつに溶け合っていた。