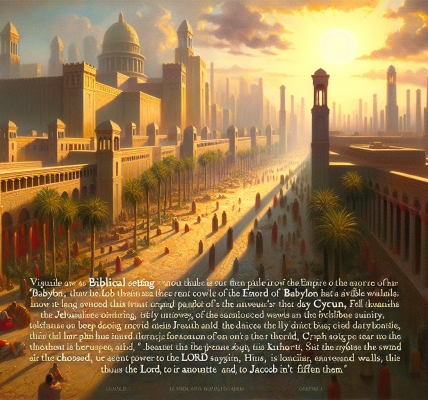ろうやの冷気が石壁を伝い、土牢の底へと忍び寄っていた。狭い窓から差し込む灰色がかった光が、床に散らばったわらの一本一本をかすかに浮かび上がらせる。パウロは震える指で羊皮紙を押さえた。右腕には、長年の鎖の摩擦でできた浅い傷が、薄明かりの中で鈍く光っている。
墨壺の傍らで、ランプの火がわずかに揺れた。煙がゆらりと立ち上り、彼の古びた顔を柔らかく包む。外では、ローマの夜の気配が濃くなっていた。遠くからは、兵士たちの靴音が規則正しく響いてくる。が、その音さえも、この深い静寂の中ではかすんで聞こえた。
彼は深く息を吸い、筆を執った。筆先が皮の表面に触れる感触は、いつになく重く感じられた。
「愛する子テモテへ」
筆が止まる。愛する子――この言葉が、彼の胸の奥で温かい塊のように広がった。テオケルヤの家のことを思い出した。あの小柄で、少し内気そうな青年が、熱心に彼の話に耳を傾けていた姿が、瞼の裏に浮かぶ。リュステラで出会った頃のテモテは、まだ若かった。母親ユニケと祖母ロイスから受け継いだ信仰は、彼の瞳に静かな確信として宿っていた。
「わたしは、昼も夜もあなたのことを祈りのうちに覚え、涙を流しながら、あなたに会いたいと願っている」
実際、彼の頬を一筋の涙が伝った。それは老いのせいだけではなかった。エペソに残したテモテが、今どのような重圧に直面しているかを思うと、胸が締めつけられるような思いがした。異なる教えが蠢き、人々の愛が冷めていくという報告が、幾度か彼のもとに届いていた。あの優しい心を持つ青年が、羊の群れを守る牧者として、荒れる風と対峙している。
ランプの火がぱちりと音を立てた。彼は再び筆を進める。
「ですから、私はあなたに勧めます。神の賜物、すなわち、私の按手によってあなたのうちにあるものを、再び燃え立たせてください」
按手の日のことを、パウロはありありと思い出した。エペソの会堂で、彼の額に手を置いた時の、あの厳粛な瞬間。祈りと共に、責任が移された実感。しかし賜物は、薪のない火のように、放っておけばいつか弱くなる。それは彼自身が、アラビアの荒野で、あるいはアンテオケの迫害の中で、幾度も経験したことだった。
「神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です」
書いている言葉が、まるで彼自身の魂を再び鼓舞しているように感じた。この石牢の中でも、確かにその霊は働いていた。恐怖は、床下から這い上がる冷気のように確かに存在した。明日はどうなるか、ネロの気まぐれがいつこの命を奪うか。それでも――それでも、胸の奥に揺るがない炎があった。それは彼がダマスコ途上で出会った光から始まり、今も消えることなく燃え続けている。
彼はうつむき、肩の傷がうずくのを感じた。鞭の跡である。それでも口元には、かすかな笑みが浮かんだ。なぜなら、彼が今書いているこの信仰の言葉は、彼で始まるものでも、彼で終わるものでもないからだ。ロイスからユニケへ、ユニケからテモテへ。そして今、彼からテモテへ。それは清い流れのように続いていく。
夜は更け、ランプの油が尽きかけている。彼は最後の力を振り絞るように、筆を走らせた。
「あなたは、私から聞いた健全な言葉の型を、キリスト・イエスにある信仰と愛をもってしっかり守りなさい。あなたにゆだねられている良いものを、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい」
羊皮紙の上に、彼の思いが一滴の雫のように落ち、墨の輪がわずかに広がった。それは計画的なものではなかった。人間の手によるものには、必ずこうした偶然の跡が残る。
彼は書き終え、巻き物をゆっくりと巻いた。革紐で丁寧に結ぶ。この手紙が、海を越え、町を行き、テモテの手に届くまでには、長い旅が待っている。運び手のクロエの兄オネシモロスが、細心の注意を払ってくれるだろう。
ろうやの隅で、一匹の鼠がわらをかすかに動かす音がした。パウロは巻き物を胸に抱き、目を閉じた。祈りが、沈黙のうちに彼の唇をゆるめた。
遠くエペソでは、おそらくテモテも今、同じ星空の下で、彼のことを思い、祈っているに違いない。それだけの確信が、この冷たい石の部屋に、かすかな温もりをもたらしていた。信仰の連鎖は、鎖とは違う。人をつなぐものでありながら、自由にする。彼はそのことを、この身をもって知っていた。
やがて、新しい日が、狭い窓から差し込むだろう。その時まで、彼はこの小さな巻物を胸に抱いたまま、静かに時を待つのだった。