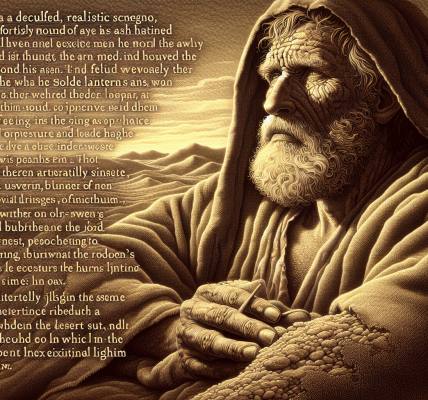夕暮れが、ギルアデの丘陵を柔らかな葡萄酒色に染めていた。ヤコブは、ひび割れた手で最後の一束の大麦を縛り終えると、鍬を地面に突き刺し、深く息を吸った。収穫の匂い——乾いた土、穂の甘い香り、そして自分自身の汗の塩気——が鼻腔を満たした。今年もまた、土地は確かに与えられていた。その重い安心感と共に、毎年訪れるあの複雑な思いが、胸の奥からわき上がってくるのを感じた。収穫は祝福の証しだが、それは同時に、覚え、分かち、清くあれ、という呼びかけの始まりでもあったのだ。
翌日、ヤコブは息子のエリアフを連れて、家畜の囲いへ向かった。雄羊の購入を考えていた。祭りが近づいている。エルサレムへ巡礼に出る前に、肉を家族で食べ、また一部を近隣の貧しい者たちと分かち合うためのものだ。「覚えておけよ、エリアフ。ただ獣なら何でも良いわけではない」と、ヤコブは囲いの柵に肘をつきながら言った。「主がわたしたちに与えられた地で食べるものは、主が定められたものだ。それはわたしたちが、他のあらゆる民と異なる、聖なる民であることの印なのだ」
エリアフは真剣な面持ちでうなずき、父の言葉に耳を傾けた。ヤコブは指を折りながら、子どもの頃から父から聞かされ、今では自分が口にする言葉をゆっくりと繰り返した。「分かれた蹄があり、反芻するもの…それは食べてよい。牛、羊、山羊、鹿に羚羊…。しかし、らくだや岩狸、野兎は反芻するが蹄が分かれていない。それは汚れたものだ。豚は…」 ヤコブは少し間を置いた。「豚は蹄は分かれているが、反芻しない。その肉にも触れてはならない」
エリアフが小さく呟いた。「でも、砂漠を越えてくる商人たちは、豚肉を焼く臭いをさせていたよ」
「そうだな」とヤコブは目を細めた。「彼らは彼らのやり方で生きている。しかし、我々は違う。我々はエジプトの奴隷の家から、主が力強い御手をもって導き出された民だ。この食べるという行為さえも、その自由と選びの記憶を刻み続けるためのものなのだ。覚えているか、祖父が言っていたことを。『口に入るものは心にも入る』と」
二人は、蹄の形を確かめ、しっかりとしたよく動く雄羊を選び出した。その帰り道、ヤコブは空を見上げた。大空を鷲が悠々と輪を描いている。彼はまた言葉を続けた。「鳥についても同じだ。鷲、ハゲワシ、黒鷲、隼…こうした猛禽は食べてはならない。不浄なものを喰らうからだ。しかし、鳩や山鳩は…」 彼はふと、過越の祭りに捧げた二羽の山鳩を思い出し、胸が少し熱くなった。「…それは清い。主へのささげものにふさわしい」
数日後、巡礼の準備は佳境に入っていた。妻のリブカは、小麦粉を練り、種入れぬパンを焼いていた。ヤコブは、収穫したばかりの小麦、新しい葡萄酒、搾りたてのオリーブ油を、それぞれ十分の一ずつ取り分け、頑丈な袋に詰めていた。エルサレムへの長い道のりの荷物だ。もう一つの十分の一は、すでに町の城門のそばに住むレビ人と、寄留している孤児、寡婦に渡している。彼らには土地の相続分がない。主の定めは、食べ物の問題を超えて、共同体の裂け目を繕うための知恵でもあった。
「お父さん」と、末の娘ミリアムが、ざくろを持って台所から走ってきた。「このざくろ、大きいでしょう? エルサレムに持っていくの?」
ヤコブは娘の頭を撫でた。「いや、これはここで食べるのだよ。エルサレムでは、主の選ばれた場所で、主の御前で、取り分けた十分の一の穀物や葡萄酒、それにこの雄羊で祝う。そして家族も、使用人も、レビ人も一緒に食べ、主を喜び祝うのだ」
ヤコブの心は、まだ見ぬエルサレムの神殿の丘へと先走った。そこは、部族の区別を超え、イスラエル全体が一つとなって主を礼拝する場所だ。巡礼の道中、野原で死んでいる獣を見かけることもあるだろう。その肉に触れるなら、衣服を洗い、水で身を清め、日没まで汚れた者とならねばならない。それは、生と死、清さと汚れの境目を、日常的に意識させるための律法だ。生活のすべてが、神の前における自分の立ち位置を問いかけているようだった。
出発の前夜、家族は囲炉裏を囲んで座った。雄羊の肉が炭火で焼かれ、いい匂いが家に満ちている。ヤコブは杯を取り、新しい葡萄酒を注いだ。「主をほめたたえよ」と彼は静かに祈った。「この地の実りを与え、清いものと汚れたものを教え、寄る辺なき者を忘れないように命じ、そしてご自身の名を置くために一つの場所を与えてくださった主を。」
彼は目を開け、柔らかな炎の光に照らされた家族の顔を見渡した。幼いミリアム、成長しつつあるエリアフ、黙ってうなずくリブカ。これらの規定は、決して重い枷ではなかった。それは、荒野で彷徨った父祖たちへの憐れみから始まり、約束の地での彼らの生き方を形作る、一種の大きな物語の筋書きだった。何を食べ、何を避け、収穫の何をどこに運ぶか——その一つ一つが、「あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主があなたをそこから導き出された」という、たった一つの核心的な記憶へと、紐で結ばれて戻ってくる。
雄羊の肉が切り分けられ、家族の皿に載せられた。ヤコブはそれを口にした。野生的で濃厚な味わいが広がる。これは清いもの、主が与えられた祝福の味だった。そして彼は思った。主の定めは、胃袋を通して心を形作り、行いを通して共同体を固め、巡礼を通して一つの民としての自覚を更新する。それは、単なる規則の羅列などではなく、この民を「わたしのもの」とする、神の執拗なほどの愛の文法なのだ、と。
外では、ぎんぎん星座がギルアデの山々の上で瞬いていた。明日から始まる長い旅路と、そこで待つ喜びを思い、ヤコブの心は静かな高揚に包まれた。彼はまた、取り分けられた袋に目をやった。それは単なる荷物ではなく、感謝の応答であり、選びの証しであり、約束そのものの重さを運ぶものだった。