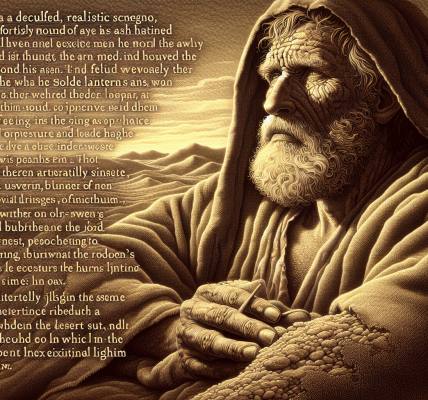オリーブ畑の縁に立つエルアザルは、夜明け前の暗がりで外套をまとった。東の山脈の稜線が、まだ紺碧の闇に沈んでいる。彼は理由もなく、むしょうに山頂へ登りたくなった。老いた膝はうずくが、胸の内でささやく声に逆らえなかった。羊皮の水筒を肩に、樫の杖を頼りに、小径を登り始める。
歩みとともに、闇が薄らいでいく。最初に気づいたのは星々の囁きだった。天の高いところで、幾千の光が震えている。それは軍勢の行進のように整然としていながら、一つひとつが独特のリズムで瞬く。詩編の言葉が彼の唇に浮かぶ。「天にあるものよ、主をほめたたえよ。いと高きところで、主をほめたたえよ。」
風が起きた。夜明けを運ぶ風だ。それは谷間を駆け抜け、老いた柏の木々を揺さぶり、葉を震わせてざわめきを立てる。そのざわめきが、まるで祈りの合唱のようにエルアザルに聞こえた。風は御名を運ぶ使者なのだ、と彼は思った。
東の空が溶け始めた。最初はほんのりと臙脂色が滲み、やがて珊瑚色、黄金へと変わる。太陽が山の背を昇る瞬間、すべてが息をのんだ。光の刃が一気に谷間を貫き、岩肌を焼き、露をきらめかせる。エルアザルは目を細めた。「太陽よ、月よ、主をほめたたえよ。輝く星よ、主をほめたたえよ。」
すると、鳥たちの歌が始まった。最初は一羽のひばりの高い鳴き声。それに応えるように、茂みから鵯のさえずり、崖から鷹の鋭い叫び。歌は重なり、絡まり、一つの壮大な賛美歌を織りなす。彼は思わず笑みを浮かべた。これこそ、命あるものの自然な礼拝だ。
山頂に着いた時、彼の周りでは小さな世界が目覚めていた。岩陰では蜥蜴が身を延ばし、苔の上を甲虫が這う。遠くの平野では、羊の群れの鈴の音が風に乗って聞こえる。村々からは朝の炊煙が立ち昇り、人々の活動の始まりを告げている。
エルアザルは岩に腰を下ろし、水筒の口を緩めた。眼下に広がる世界——山々と谷、川と森、野と町——すべてが光の中で息づいている。彼は深く息を吸い込んだ。冷たい空気が肺に染み渡る。ここには、何一つ無駄なものはない。全てがその存在そのもので、造り主への証しを立てている。
「海の怪物よ、すべての深淵よ。火と雹、雪と霧、あらゆる山々、すべてのケデルの木、獣とすべての家畜、這うものと飛ぶ鳥——」
彼のつぶやきは風に消えたが、心の中では聖句が完結した。そして彼自身も、この賛美の輪に加わっていることを悟った。老いた体、震える手、遠のく記憶——それさえも、あるがままに主をほめたたえるための器なのだ。
日が高くなるにつれ、山の斜面に人の気配が増してきた。羊飼いが群れを連れて登ってくる。麓の村からは、子どもたちの声がかすかに聞こえる。王も乞食も、老人も若者も、今日という日に息を吹き込まれている。人間の賛美は、時に言葉になり、時に仕事になり、時に沈黙になる。それでも確かに、被造物の合唱に加わる一つの声なのだ。
エルアザルはゆっくりと立ち上がった。膝の痛みは消えていないが、心は軽い。下山の途で、彼は小さな泉のそばに足を止めた。水は岩の間から湧き出し、銀の糸のように流れ落ちている。その音は、絶えることのない祈りのようだった。
彼がふと目を上げると、一本の野生の杏の木が風に揺れていた。枝には青い実がいくつもぶら下がっている。来年の春にはまた花を咲かせ、実を結ぶのだ。すべてが循環し、すべてが賛美する。
夕暮れが近づき、エルアザルは自分のオリーブ畑に戻ってきた。暗くなり始めた空には、最初の星がまたたいている。家の中からは、妻が用意した夕食の匂いが漂ってくる。
彼は戸口で靴を脱ぎながら、ひとりごちた。
「天も地も、すべてのものは御手から生まれた。そしてすべてのものが、御名を呼び続けている。」
ろうそくの灯りが窓に揺れる。どこか遠くで、野犬の遠吠えが聞こえた。それさえも、この壮大な夜の賛美歌の一部のように思えた。エルアザルは深くうなずき、暗闇に包まれた世界が、見えざるハーモニーを奏でているのを感じた。