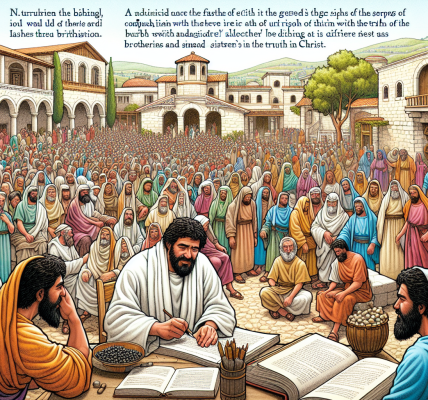**詩篇13篇に基づく物語:闇の中からの祈り**
ユダの山地に広がる深い森の中に、ダビデという名の若い羊飼いがいた。彼はかつてサウル王の宮廷で竪琴を奏で、人々から愛されたが、今は王の怒りを買い、荒れ野や洞窟を逃げ回る身となっていた。ある夜、ダビデは暗い洞窟の中に身を潜め、冷たい岩壁に背を預けながら、胸に渦巻く苦しみを神に訴えていた。
「主よ、いつまで私を忘れておられるのか。いつまで御顔を隠されるのか。」
彼の声は洞窟に反響し、孤独と絶望がさらに深まったように感じられた。外では風がうなり、木々の葉がざわめき、まるで彼の心の混乱を映し出しているようだった。ダビデは両手で顔を覆い、涙が頬を伝った。
「私の魂に謀りごとを巡らせ、敵が私の上に勝ち誇るまで、いつまで私を嘆かせるのか。」
彼の敵はサウル王の兵士たちだった。彼らはダビデを「王位を狙う謀反人」と叫び、執拗に追いかけ回した。かつては神の油注がれた王サウルに仕え、忠誠を尽くしたのに、今では命を狙われる身。その理不尽さに、ダビデの心はかき乱されていた。
「主よ、私の神よ、私に目を注ぎ、私に答えてください。私の目を光らせ、死の眠りにつかせないでください。」
彼の祈りは次第に熱を帯びた。洞窟の奥からは水滴が落ちる音だけが響き、静寂が支配していた。しかし、ダビデはその静けさの中に、神の臨在を感じ始めた。彼は幼い頃から、羊の群れを導きながら、神と語り合ってきた。今も、神が共におられることを信じようとした。
「私の敵が『彼に勝った』と言い、私が揺らぐとき、彼らが喜ばないようにしてください。」
彼は拳を握りしめ、心の中で敵の嘲笑を打ち破ろうとした。しかし、真の勝利は剣や策略ではなく、神の御手にかかっていることを思い出した。ダビデは深く息を吸い、竪琴を手に取った。指先で弦をはじくと、優しい音色が洞窟に広がった。
「しかし、私はあなたの慈しみに信頼します。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌をうたい、主が私を良く扱ってくださったからです。」
祈りが賛美へと変わる瞬間、ダビデの心に平安が訪れた。外ではまだ風が吹き荒れ、敵の足音が遠くに聞こえるかもしれない。しかし、彼はもう恐れなかった。神が共におられる限り、闇は決して永遠には続かない。
やがて夜が明け、薄ら光が洞窟の入り口に差し込んだ。ダビデは立ち上がり、新たな決意を胸に外へと歩き出した。彼の目には、再び希望の光が宿っていた。