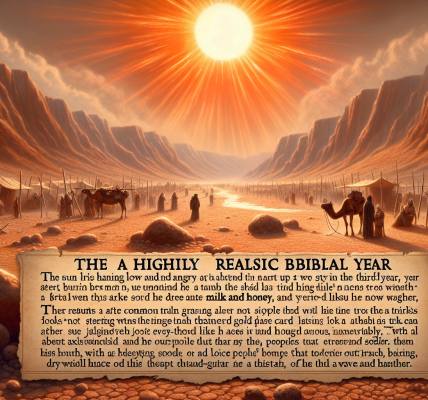エルサレムへの道は、砂漠の熱気に歪んで見えた。パウロは額の汗をぬぐいながら、足元の小石が転がる音に耳を傾けていた。バルナバと若いティトスを連れたこの旅は、単なる巡礼以上の重みを帯びていることを彼は痛感していた。風が渓谷を通り抜け、枯れ草を揺らす音が、まるで過去の議論のこだまのように聞こえた。
十四年目の春――かつてダマスコ途上で出会ったあの光以来、彼の内側には消えない確信が宿っていた。異邦人にも無条件で開かれた福音を、今こそエルサレムの柱たちと確認する時が来たのだ。
エルサレムの城壁が視界に現れると、ティトスが不安げに呟いた。「彼らは俺のようなギリシャ人をどう見るだろうか」
パウロは彼の肩を叩きながら答えた。「割礼の有無など問題ではない。キリストにある自由こそが真実なのだ」
街中には祭りの準備をする人々の喧騒が満ちていた。ヤコブの家はオリーブの木陰にひっそりと建ち、中からは複数の声が聞こえてくる。扉を開けると、煤けたランプの灯りの中に、ペテロのたくましい影が浮かび上がった。
「よく来た、兄弟よ」
ペテロの抱擁には野性の温もりが残っていた。ヨハネの沈黙深い眼差し、ヤコブの指にインクの染み――使徒たちの営みが部屋の空気に滲み出ている。
議論は深夜まで及んだ。パウロが異邦人への宣教の実りを語ると、ヤコブが細く刻んだパピルスを手に取った。「アンティオキアで起きていることについて、幾つかの報告が届いている」
パウロは杯の水を一口含み、喉の渇きを潤した。「彼らは聖霊の証印を受けた。それだけで十分ではないか」
次の日、共同の食事で緊張が表面化した。初めは笑い声の絶えなかった食卓が、エルサレムから訪れた一団が加わると急に静かになった。ペテロが異邦人と共にいた席から徐々に距離を置き始めるのを、パウロは鋭く見逃さなかった。
「あなたはユダヤ人でありながら、なぜ異邦人のように振る舞うのか」
パウロの声は静かだが、石を投げるように明確だった。食卓全体が凍りついた。
ペテロの頬が微かに紅潮した。「状況を理解していないのか、パウロ?」
「むしろ理解しすぎている」パウロは立ち上がり、傷ついた雄獅子のような眼光を向けた。「あなたは福音の真理に反して、人を欺いている」
沈黙が部屋を満たす。窓の外では商人の叫び声が聞こえ、日常は何事もなく流れ続けている。ティトスが無意識に自分の無割礼の手を見つめている。
パウロの言葉が再び響いた。「人は律法の行いによってではなく、キリストへの信仰によって義とされる。もし義が律法を通して得られるなら、キリストの死は無意味だったことになる」
その瞬間、ランプの炎が揺れ、壁の影が踊った。ペテロの肩の力が抜け、深いため息が零れた。十年近く前にヨッパで見た幻――天から下ろされた清くない動物の入った敷布――を彼は思い出していたのかもしれない。
「あなたは正しい」ペテロの声はかすれていた。「私たちはユダヤ人であれ異邦人であれ、同じパンから共に食べるべきだった」
夕暮れが青紫色のベールをエルサレムに落とす頃、二人は中庭の井戸端に座っていた。水を汲む紐のきしむ音が規則的に響く。
「あの日、あなたが御顔を見ずにエルサレムを去った後、私はずっと考え続けていた」パウロが言った。「私たちは皆、キリストに生かされるために死んだ者たちだ。もはや私が生きているのではなく、キリストが私の内に生きておられる」
ペテロは手のひらを広げ、そこに残る漁師時代の傷跡を見つめた。「時として、古い習慣は第二の天性のように感じられる。だが主は私たちに新しい命を下さった」
夜風が吹き抜け、遠くで子羊の鳴き声が聞こえた。過越の準備である。パウロは思った――かつて律法が指し示していた小羊は、今や現実のものとなった。この自由の福音を、ユダヤ人にもギリシャ人にも、奴隷にも自由な身分の者にも、等しく告げ知らせなければならない。
月明かりが石畳を照らす中、パウロは宿に戻る道を歩きながら、異邦人たちの共同体で共有した無酵母パンの味を思い出した。あの単純な食事に込められた恵みの深さを――それはエルサレムでもアンティオキアでも、いや地の果てにおいても変わることのない、一つの真理の味だった。