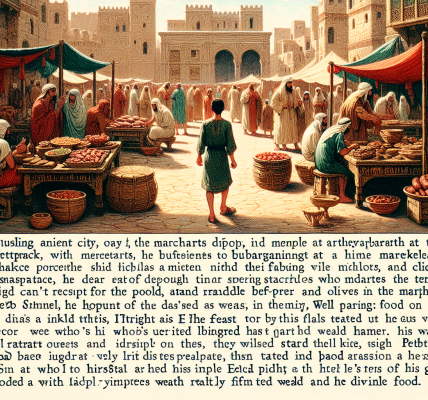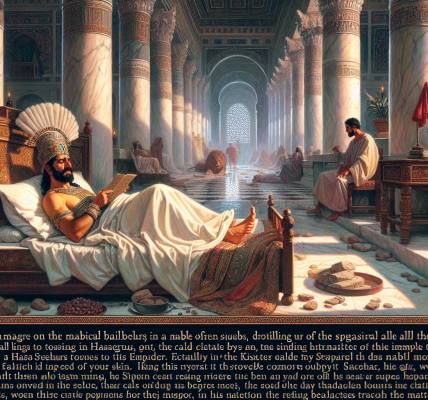岩の隙間から洩れる冷たい風が、頬を刺す。ダビデは膝を抱え、洞窟の奥深くに身をひそめていた。足元では、昨日からの雨水が細い流れとなり、闇の中へと消えていく。サウルの追手たちの声は、もう半日ほど聞こえていない。が、油断は禁物だった。彼は静かに息を吸い、肺に湿った土の匂いを満たした。この逃亡生活は、いつまで続くのか。かつては羊の群れを導くために通ったこの荒野が、今は死の罠と化している。
思い起こせば、あの日からだった。油を注がれ、イスラエルの将来を約束されながらも、今はこうして獣のように狩られている。夜、天幕を抜け出して祈るとき、喉の奥から沸き上がるのは、怒りでも諦めでもない。ある種の渇き、底なしの渇きだった。父よ、と彼は唇を動かした。声には出さない。ただ心の内で、岩のように重たい言葉を積み上げていく。なぜ、私はここにいるのか。なぜ、あなたの選んだ僕が、穴の中に隠れねばならないのか。
すると、ふと、遠くで雷鳴が滾る音がした。いや、雷ではない。もっと深く、地の底から湧き上がるような轟きだ。ダビデは顔を上げた。洞窟の入口から見える空は、さっきまで灰色だったのに、今は濃い藍色に変わり、雲が渦を巻き始めている。風の音が変わった。優しい揺らぎから、鋭い唸りへ。彼の髪の毛が逆立つのを感じた。
その時、彼の内側で何かが崩れた。長く溜め込んでいた恐惧、疑問、孤独が、一瞬のうちに堰を切った。彼は跪き、額を冷たい岩に押し当てた。父よ、と今度は声にした。その声は震え、洞窟の壁に反響した。私は死の縄に巻かれ、滅びの洪水が私を襲います。よみの綱は私を取り囲み、死の罠は私に出会った。助けてください。あなただけが、私の岩、我的巌、私の逃げ場です。言葉が次々と溢れ出る。整った祈りではなく、砕かれた心の欠片が、そのまま叫びとなって迸った。
すると、驚くべきことが起こった。外の轟音が急に大きくなり、洞窟全体が震え始めた。ダビデは慌てて入口へ駆け寄った。目の前の光景に、息を呑んだ。荒野全体が神の怒りに燃えているようだった。厚い雲が低く垂れこめ、その間を鋭い閃光が切り裂く。稲妻は弓矢のように地上を射貫き、雷鳴は神の声そのもののように天地を揺さぶる。そして雨。鉄槌のように打ち付ける激しい雨。それは、単なる嵐ではなかった。ダビデの目には、それが神の御手の動きとして見えた。稲妻は神の矢、雷鳴は御声の轟き、激流は御鼻の息のように思えた。
彼は恐怖に打たれながらも、一歩も引かなかった。むしろ、その全身でこの顕現を感じ取ろうとした。風が彼の外套を激しく揺らし、雨粒が顔を打つ。そのすべてが、冷たくもあり、また驚くほど生々しく力に満ちていた。そして、最も深い闇の中から、一筋の光が差した。いや、光というよりは、闇そのものを引き裂くような、確かな臨在の感触。それは、目には見えぬが、肌に触れる熱として、鼓動と共鳴する響きとして、彼の内に浸透してきた。
「呼べ。さらば、我汝に応えん。」
その言葉は、雷鳴の中にあったのではない。彼自身の胸の奥で、静かに、しかし揺るぎなく鳴り響いた。ダビデは突如として力を得た。それは、自分の腕力や戦術などではない。外から注がれる、圧倒的な強さだった。疲れていた足腰に、奔流のような活力が満ちる。震えていた手が、岩のように固くしまる。彼は洞窟を出た。雨はまだ激しく、風は彼を引き留めようとするが、彼の歩みは妨げられない。まるで神ご自身が、彼の前に道を開き、足場を固めてくださるかのようだった。
前方に、数人のサウルの兵士の影が見えた。彼らもまた、突然の天変に慌てふためき、盾を頭上に掲げていた。ダビデは走り出した。走るというより、風に乗って滑るように。手にした投石器が、いつもより軽く感じられる。石を込め、振り回す。その動作は、流れるように滑らかで、的を捉えるべく放たれた石は、嵐の轟きの中でも鈍い音を立てて命中した。彼は戦っていたが、しかし、不思議と殺意はなかった。これは、自分自身の戦いではなく、自分を通して現される、もう一つの戦いなのだと悟った。敵は崩れ、逃げ惑う。彼らが恐れているのは、ダビデという一人の男ではない。この荒野全体に満ちている、計り知れない威厳だった。
嵐は去り、荒野に静寂が戻った。雨上がりの泥土の匂いが漂う。ダビデは一人、ぬかるみに立ち、深く息を吸った。空は洗われ、夕焼けが広がり始めていた。彼の衣服は泥にまみれ、体はあちこち打ち身だらけだったが、心はかつてないほど軽く、澄み切っていた。あの洞窟の中の渇きは、今、命の泉に変えられていた。
彼は近くの小高い岩の上に登り、西に沈む太陽を見つめた。父よ、と彼は呟いた。今度の声には、震えも渇きもなかった。あなたは私の燈火。あなたは私の闇を照らされる。あなたによって、私は軍勢を駆け抜け、私の神によって、私は城壁を飛び越える。あなたの道は完全、あなたの言葉は純粋。あなたは、すべてあなたに避けどころを求める者の盾。
風がそっと彼の頬を撫でる。それはもう、鋭い唸りではなく、慈愛に満ちた囁きのように感じられた。ダビデは目を閉じた。彼の内側には、一編の歌が形づくられ始めていた。岩と救い主についての歌。それは、後の世に「詩篇」として記されることになる、感謝と驚嘆の旋律の最初の一節だった。彼はまだ多くの戦いを経ねばならない。王冠は遠い先のことだ。しかし、この瞬間、この泥と輝きの中に、一つの確信が根付いた。彼の岩は動かず、その避けどころは永遠に堅く立っている。夕闇が迫る荒野で、ダビデは静かに笑みを浮かべた。そして、これから歩む長い夜道のため、新たな力を胸に刻み込んだ。