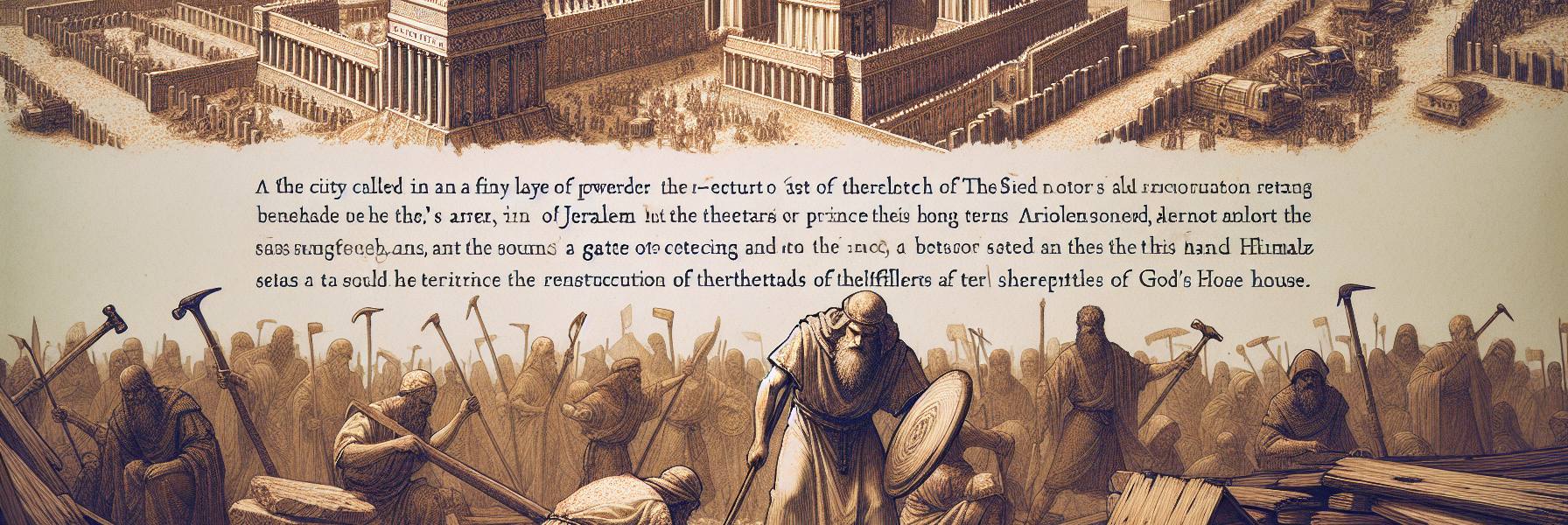埃が舞い、瓦礫の間にわずかに残る道を、男たちの一団が歩いていた。帰還、という言葉が軽すぎる。バビロンの地で生まれ、父祖の言葉を聞きながら育った者にとって、この荒れ果てた丘は故郷でも何でもなかった。ただ、血の中に刻まれた呼び声に引きずられるように、彼らは来たのだ。ユダの族長の子ら、祭司、レビ人、それに神殿に仕える者の子孫たちが。
その先頭にいたのは、アズリクァムという男だった。背は高くないが、肩幅が広く、長い旅の疲れを感じさせない歩幅で進む。彼の父は、バビロンで息を引き取る間際、繰り返しつぶやいた。「城壁の門…北の…」。アズリクァムには、その門の記憶などない。ただ、父の目に浮かんだ郷愁の色だけが、手に持った羊皮紙の系図とともに、重く心にのしかかっていた。
ようやくエルサレムの跡らしき場所に着くと、人々はただ呆然と立ちつくした。かつての栄華を伝えるものは、切り立った石の土台と、所々に残る黒く焼けた木材だけだ。風が吹き抜ける音だけが、不気味に響く。
「…ここか。」 誰かが呟いた。
アズリクァムは黙って、腰に下げた革の筒から、もう一枚の皺くちゃな紙を取り出した。そこには、細かい文字で名前が列記されている。『エルサレムに住んだ者らは次のとおりである。ユダの子ら、ベニヤミンの子ら、エフライムとマナセの子ら…』 彼は声に出して読みはじめなかった。ただ、目で文字を追いながら、この廃墟の中に、かつて息づいていた無数の生を想像しようとした。名前の向こうに、顔があり、声があったはずだ。
数日が過ぎ、少しずつ生活の拠点ができはじめた頃、アズリクァムの元に、ヨナタンという名の年老いたレビ人が訪ねてきた。彼はかつての神殿の歌声を、わずかながら記憶していたという。目は白濁しているが、声には力があった。
「門衛はね、若い者よ」 ヨナタンは、まだ整地も終わらない空地に腰を下ろしながら言った。「ただ扉を開け閉めするのではない。朝の最初の光が東の山の端を捉える時、誰よりも早く起きて、主の庭の戸を押し上げる。それは…祈りに等しい行為なんだ。」
アズリクァムは系図を広げ、ヨナタンの指さす名前を見つめた。メシュレムヤ。コレ。シャルム。長い名簿だ。彼らは皆、この場所で、朝ごとに同じ動作を繰り返していたのだろうか。
「そして祭司たち」 ヨナタンの声が続く。「アマルヤの子、マアセヤ。彼の仕事は…聖所の道具を守ること。金の燭台、供えのパンの机…。捕囚に出発する前夜、彼の祖父は、布に包んだ器物を、地下の隠し場所に納めたと言う。もう誰もその場所を知る者はおらんがな。」
物語は、名簿という乾いた骨格に、肉付けされていった。ある者は小麦粉を練って供えのパンを焼く係。ある者は香料を調合する微妙な技を受け継ぐ者。ある者は歌うことだけを、代々の務めとしてきた家系の者。彼らは皆、この荒れ野に帰ってきた。それぞれが携えてきたのは、わずかな荷物と、くすぶり続けた信仰の火種だけだった。
日々は過酷だった。食糧は乏しく、周囲には敵意を持つ民もいた。ある夜、アズリクァムは見張りに立っていた。遠くでジャッカルの遠吠えが聞こえる。彼は、自分の番が明けるのを待つシャレムという若者のことを考えた。彼はベニヤミン族の出で、系図には『兄弟たちの長』とあった。実際、彼は自然と人をまとめる才を持っていた。争いが起こりそうになると、低く響く声でなだめ、公平に仕事を振り分けた。
月日は流れ、粗末ながらも祭壇が築かれ、最初の犠牲の煙がゆらゆらと立ち上った日、人々は泣いた。煙は薄く、風にすぐに散ってしまうものだったが、それは七十年来、絶えていた生きた信仰の証だった。
アズリクァムは、あることを思い立った。彼はヨナタンと共に、可能な限りの古老を尋ね歩き、彼らの断片的な記憶を、あの系図の名の傍らに注釈のように書き加えはじめた。『メシュレムヤ:東の門の鍵を預かる。声が低く、合図の角笛を吹く時、遠くまで響いたという』 とか、『マティトヤ:供えのパンを焼く。父の伝えた秘伝は、オリーブ油に少量の蜂蜜を加えること』 といった具合だ。
それは、神学的な記録というより、一人の人間が、名前に宿った命の痕跡を探す作業だった。彼は時々、書きながら、彼らがどんな失敗をし、どんな喜びを味わったのかを空想した。完璧な聖職者などいなかっただろう。苛立つ日も、無気力になる日もあったに違いない。それでも、彼らは『務め』を、呼吸のように繰り返した。
数年後、少しずつ共同体が形を成したある夕暮れ、アズリクァムは完成した写本を抱えて、再建された神殿の前の広場に立った。それはもはや、単なる名簿ではなかった。失われた都市の、一片の記憶の再構築だった。彼はその巻物を、これから来る世代に渡すために、聖所の櫃に納めようと考えていた。
風が吹き、彼の髪を揺らす。彼は目を閉じた。父が夢見た北の門は、まだ石積みの途中だ。しかし、彼は今、別の「門」を見た気がした。それは、過去と現在をつなぐ、目に見えない扉だった。そして彼自身、アズリクァムという名が、この巻物のどこかに、未来の誰かによって書き加えられる日が来るかもしれない。その時、彼はただ『門を守る者』の一人として記憶されるだろう。それで十分だった。
彼は深く息を吸い、新しい石の階段を一歩、踏みしめた。背後から、夕べの祈りを準備するレビ人たちの、かすかな歌声が聞こえてきた。