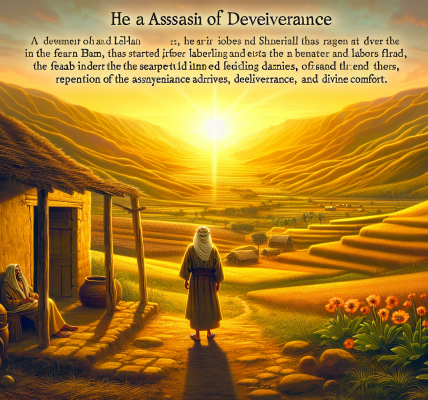山肌を焼くような太陽が、シナイの荒れ野に白い光を投げかけていた。砂は熱を持ち、遠くに見える岩山は、揺らめく蜃気楼の中にぼんやりと浮かんでいる。その乾ききった風景のただ中に、粗末な天幕が幾つも集まる小さな宿営があった。羊の毛で織られた黒い天幕の入口から、一人の男が顔を出した。ベツァルエルである。彼は目を細め、眩しい空を見上げた。今日もまた、何の変わりもない日が始まるのだろうと思った。
宿営の中には、絶え間ない生活の音が満ちていた。女たちが石臼を挽く音、子供たちの甲高い声、山羊の鳴き声。しかし彼の心には、ここ数日、ある種の落ち着きがなかった。理由はわからない。羊の皮をなめす手の動きは普段と変わらないのに、なぜか指先が、木や金属に触れたいという衝動にかられていた。少年の頃、祖父が柘植の木を彫って小さな箱を作るのを見ていたことを、ふと思い出した。あの刃物の動き、木屑の香り。忘れていた感覚が、胸の奥からゆっくりと湧き上がってくるようだった。
その日、モーセは山から下りてきた。彼の顔には、岩山の頂で直に会ったものだけが持つ、言いようのない威厳と、深い疲労が刻まれていた。民は恐れおののき、遠くから見つめるだけだった。しかしモーセは、人々を集めると、ゆっくりと語り始めた。
「主はこう言われる」と彼の声は、乾いた空気を震わせた。「見よ、わたしは、ユダ部族のフルの子であるベツァルエルを名指しで召し出した。彼に、わたしは神の霊を満たし、知恵と英知と知識と、あらゆる仕事において豊かに注いだ。金、銀、青銅の細工を考案し、はめ込みの宝石を彫り、木を彫る仕事をなすために。また、ダン部族のアヒサマクの子オホリアブを、彼の助け手として立てた。心に知恵ある者すべてに、わたしは知恵を授け、わたしが命じるすべてのものを、彼らに作らせるであろう。」
ベツァルエルは、自分の名が呼ばれたとき、足元の砂が崩れるのを感じた。周囲の視線が一斉に自分に集まる。フルの子。ただの羊飼いの、皮なめし職人の。神の霊? 彼は自分の手の平を見つめた。そこには、革紐でできた水筒を繕った時の古い傷跡が、茶色く残っていた。その平凡な、労働で節くれだった指に、神の霊が満たされるというのか。疑問よりも先に、得体の知れない畏怖が、背筋を這い上がった。
モーセは続けた。幕屋、つまり主が民の中に住まわれるための聖なる天幕について、詳細に語っていく。あの契約の箱、贖いの蓋を備えた箱。それに供える机と、その上の器具。純金の燭台と、そのともしび皿。香をたく金の壇。そして奉献の幕と、至聖所を隔てる垂れ幕。一つ一つの寸法、材料、意匠が、息つく暇もなく言葉として紡がれていく。金、銀、青銅。捻り糸で織られた亜麻布。青、紫、緋色の羊毛。獣の皮。アカシヤ材。
ベツァルエルの耳は、それらの言葉を一つも逃さなかった。奇妙なことに、モーセが語るその複雑な図面が、彼の心の中に、まるでかつてから存在していた記憶のように、鮮明に、そして自然に浮かび上がっていくのを感じた。金の燭台の枝の曲線、はめ込むべきラピスラズリの深い青、幕に施すケルビムの織り模様。それは、学ぶというよりも、思い出すような感覚だった。彼の指先が、微かに震えた。今すぐにでも、何かを作り始めたい。その衝動が、体の芯から沸き起こってきた。
その日の夕方、ベツァルエルは自分の天幕に戻り、火ばちの揺らめく光をぼんやりと眺めていた。隣の区画からは、オホリアブという、若くて器用な織物職人の声が聞こえてきた。彼もまた、呼び名が挙げられ、戸惑いと興奮の中で一夜を過ごしているに違いない。助け手として。二人で、そして、心に知恵が与えられたすべての者たちと共に。その言葉が、彼に少しばかりの安堵を与えた。これは、彼一人の重荷ではないのだ。
次の日から、宿営の様相が一変した。モーセから詳細な指示を受けたベツァルエルとオホリアブを中心に、ある種の聖なる喧騒が始まるのだ。工房となる区画が設けられ、各部族から献納された材料が集められ始めた。女性たちが紡いだ亜麻糸、男たちが持ち寄った金や銀の飾り、砂漠を旅する商人から入手した珍しい染料や香料。それらが、一か所に山のように積み上がっていく。
ベツァルエルは最初、金の延べ板を手に取った。その重み、冷たさ。炉で熱せられ、柔らかくなったその金属が、金槌と鏨の下で、思いのままに形を変えていく。それは、驚くほど自然な行為だった。まるで、彼の手が、金という素材の言葉を理解しているかのように。ひと敲き、ひと敲きが、無駄なく、迷いなく、完成のイメージへと近づいていく。ある時は繊細な花びらを、またある時は力強い枠組みを。彼の傍らでは、オホリアブが色とりどりの糸を機にかけ、複雑な模様を織り出していった。その手つきは確かで、神が命じられた通りの配色が、見事に再現されていく。
作業は日々続いた。朝、まだ星が淡く光る頃から、夕闇が岩山を紫に染める頃まで。槌の音、鋸の音、織機の音が、宿営にリズムを与えた。彼ら職人たちの間には、言葉をあまり交わさなくても通じ合う、静かな共感が流れていた。誰もが、自分に与えられた仕事に、ただひたすらに集中していた。それは、単なる建造作業ではなかった。神が住まわれる場所を、この地上に作り出すという、途方もない務めだった。
そんなある日、作業が佳境に入っていた頃、モーセが再び彼らのもとを訪れた。彼は、ほぼ完成に近づいた金の燭台を、じっと見つめていた。七つの枝は均整がとれ、アーモンドの花を思わせる飾りは、息をのむほどに精緻だった。長い沈黙の後、モーセは深く息を吸い、静かに言った。
「主は言われる。お前たちは、わたしの安息を守らなければならない。それは、代々にわたる永遠の契約のしるしである。それはわたしと、お前たちの間のしるしであり、わたしが、お前たちを聖別する主であることを知るためのものだ。六日の間、仕事をせよ。しかし七日目は、主のための厳かな安息である。」
ベツァルエルは、手に持っていた鏨をそっと置いた。安息。その言葉は、激しい創作の熱の中にいる彼に、冷たい水を浴びせるようだった。彼は振り返り、積み上げられた材料、削りかけの木材、半分織り上がった幕布を見た。すべては、神の命令による仕事だ。しかし神は、その仕事さえも、七日目には止めよと命じておられる。
「すべて安息を汚す者は、必ず死ななければならない」とモーセの声には、悲痛な響きがあった。「その日、仕事をする者は、だれであれ、民の中から断たれる。六日の間、仕事はできる。しかし七日目は安息であり、主のための完全な休みである。」
工房は水を打ったように静かになった。今まで一心不乱に働いてきた手が、一瞬、空中で止まる。ベツァルエルは自分の掌を見つめた。この手は、神が与えられた知恵によって、聖なるものを作り出している。それなのに、その同じ神が、七日目には一切の仕事を禁じておられる。矛盾のようでもあり、また深い意味のある調和のようでもあった。神ご自身が、天地を創造した六日の後、七日目に休まれた。その創造のリズムに、今、彼らも従うことを求められているのだ。
モーセは、二枚の石の板を抱えていた。神の指によって刻まれたそれらの板には、契約の言葉が記されているという。彼は最後に、それを高く掲げて言った。
「これらのことは、主がシナイ山で、モーセに語られたものである。」
モーセが去った後も、しばらくの間、誰も動かなかった。やがて西の空が茜色に染まり始めると、ベツァルエルはゆっくりと道具を工具箱にしまい始めた。オホリアブも、織機から手を離し、未完成の布を丁寧に覆った。彼らは無言で、今日の作業を終える合図を交わした。明日はまた、金槌の音が響くだろう。しかし七日目には、この宿営全体が、神聖な静寂に包まれる。そのことを思うと、ベツァルエルの心に、荒れ野の灼熱の中では忘れられていた、どこか深い安らぎが訪れるのを感じた。作ることと、休むこと。その両方の律動の中に、彼らは確かに、呼び名を挙げられ、神と共にいるのだ。山肌はすでに陰り、最初の星が、淡く輝き始めていた。