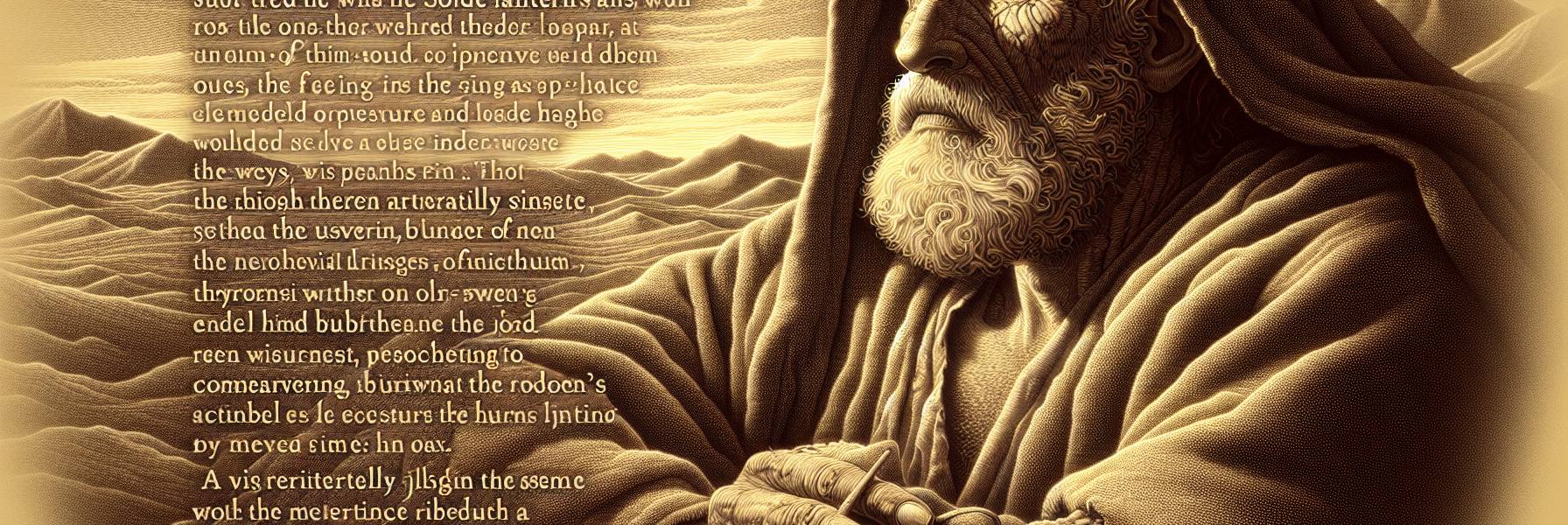今も、あの時の風の匂いを覚えている。夕暮れ時、畑仕事を終えた人々の声が遠くから聞こえ、ほこりっぽい路地を子供たちが駆け抜ける頃、西の空にオリーブの葉のように柔らかな光が広がっていた。私は町の門の傍ら、広場の一番高い石段に座ったものだ。すると、白髪の長老も、青臭い若者も、自然と集まってくる。彼らは黙って私を囲み、口を開く時を待つ。まるで、喉の渇きを覚えた羊が水場のそばで佇むように。
「さあ、話してくれ、ヨブよ。」と、一番年老いた皮革職人が、皺の深い手をひざの上に置いて言うものだった。私はためらわずに語り始める。土地の争い、家族の諍い、売買の約束が破られたこと。彼らはただうなずく。私の口から出る言葉は、冷たい泉の水のように、騒ぎを鎮め、ねじれた糸を解きほぐしていく。誰もが「ヨブが言う通りだ」と認め、心にあった角張った岩を、そっと地面に降ろした。私は彼らの目に映る、曇りなき信頼の光を見るのが好きだった。
私が通りを歩けば、若者たちは道をあけ、老人たちは起立し、貴族たちも言葉を抑えた。首領たちでさえ、私が何か語るのを恐れて、舌を押さえつけたものだ。耳のある者はみな、私を幸いな者と呼び、目のある者はみな、私に証しをした。それは、私が飢えた者を養い、孤児を助け、死にかけていた者のために祝福を叫んだからだ。やもめの心は、いつも私のために喜びの歌を歌っていた。正義を衣のようにまとい、公正を外套のように着ていた。盲目の者の目となり、足の萎えた者の足となった。
家に帰れば、それはまた別の祝福に満ちていた。敷居をまたぐと、妻の笑顔があり、子供たちの声が、蜂の羽音のように家の中を満たす。乳しぼりの時期には、岩から油の流れのように豊かであり、畑のオリーブは惜しみなく実を結んだ。私は座って、「神は私と共におられる。私の灯火が、闇夜を照らす」と確信した。全能者の密かな交わりが、私の天幕を包み、若さの力は、私の骨の中で新鮮さを保っていた。
人々は私の言葉を、春の雨を待つ大地のように待ちわびた。私は彼らに笑いかけるだけで、彼らの顔は明るくなった。私の示す道を、誰も暗くする者はなかった。それは、太陽が真昼にじりじりと照りつけるような確かさだった。彼らを選び、彼らの行く先頭に立つことは、私にとって呼吸のように自然なことだった。
…ああ、今、私はこの灰の中に座っている。肌はかさぶたと膿に覆われ、骨はいたみ、かつては光り輝いていたこの目は、底なしの闇を見つめている。あの石段は今、誰が座っているのだろう。あの広場で、かつて私の声に耳を傾けていた者たちは、今、私の前を通り過ぎる時、目をそらす。風の匂いは変わらない。夕暮れの光は、相変わらずオリーブの葉のように柔らかい。ただ、すべてが逆さまになった。祝福は苦痛に、尊敬は憐れみに、確信は問いかけに変わった。
全能者が私を囲み、その灯がまだ私の頭上にあったあの日々。私の歩みはバターで洗われ、岩は私のために油の流れをほとばしらせた。今、私の手はこの粗末な陶器のかけらで、かゆい皮膚をかきむしることしかできない。あの頃、私が町の門で座っていた場所には、今、冷たい風だけが吹き抜けている。