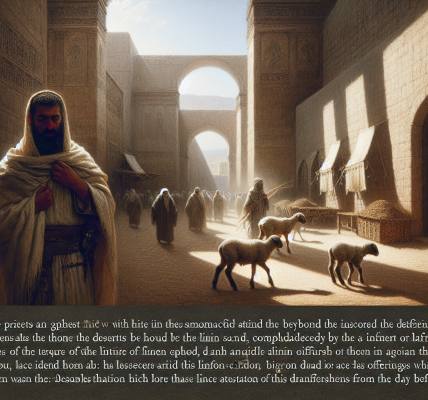岩肌の焼けるような熱さが、背中から伝わってくる。エラムは息を殺し、ひび割れた岩陰に身を潜めた。足元には、乾ききったワジの河床が白く光り、向こう側の丘には、彼を追う者たちの営みの煙が幾筋も立ち上っていた。三日。水筒の皮袋はからからで、最後の一片の干し無花果も昨日の夜に食い尽くしていた。喉の渇きは思考を曇らせ、恐怖が骨の髄までしみ込む。追手は、彼の属する部族と長年にわたる諍いを続ける者たちだ。家は焼かれ、羊は奪われ、逃げる途中で兄弟は槍に倒れた。すべては、彼の父が守り通した泉の所有権をめぐる、小さな、しかし血で塗られた争いから始まった。
「エラム、どこにいる。お前の頭には褒美がかけられているぞ」
風が運んできた嘲りの声に、体が硬直する。声はまだ遠い。だが、彼らは優秀な追跡者だ。砂漠のわずかな痕跡を頼りに、確実に距離を縮めてくる。エラムは目を閉じた。父がよく口にしていた言葉が、ふと脳裏をかすめた。「我が魂は黙して、ただ神を待つ。我が救いは神より来る」。ダビデ王の詩だ。若い頃は、羊の群れを見ながら、その調べを口ずさんだものだった。しかし今、その言葉は、空しい慰めに思えた。神はどこにいる? 兄弟が息絶えた時も、炎が家を包んだ時も、ただ黙って見ていただけではないか。
日が傾き始め、岩の影が長く伸びた。追手の気配は一度、遠のいたように思えた。エラムは躊躇いながら岩陰を離れ、かつて父が教えてくれた隠れ泉を目指して、ゆっくりと歩き始めた。かつては細い水流があったその場所は、今はただの窪みで、底には乾いた土しかなかった。膝をつき、無意識に手を伸ばす。指先に触れるのは、粉のように細かい砂だけ。腹の底から、虚無感が込み上げてきた。人間の助けも、この地の恵みも、すべては頼りにならない。彼はその場にうずくまり、顔を覆った。
ふと、幼い頃の記憶がよみがえった。大きな砂嵐の夜、父がテントの中で灯りを守りながら言った言葉。「エラムよ、見えるものすべては移り変わる。岩でさえ、風に削られて砂になる。変わらぬものは、天にいます方の約束だけだ」。その父は今、敵の捕虜となっている。その約束は何の役に立ったというのか。彼の心には怒りと絶望が渦巻いた。
夜が訪れた。砂漠の冷気が、昼の熱気を一掃する。エラムは震えながら、星のまたたく空を見上げた。あまりの星の多さに、目がくらむようだった。その時、彼は気づいた。自分がこれまで、何に信頼を置いていたのかを。家族の力、自分自身の若さと機転、この土地の知識、そして、いつかは訪れる和平への淡い期待。どれもが、嵐の中の葦のように折れてしまった。彼は自分という存在が、まるで風に吹かれる塵のように儚いものであることを、骨身に沁みて感じていた。
彼はうつ伏せになり、額を冷たい砂につけた。祈る言葉さえ出てこない。ただ、内側から零れ落ちるような思いが、静かに渦を巻いていた。助けを求める叫びでも、嘆きでもない。それは、全てを失った者が、そこにただ在る、という一点にすべてが凝縮された、静かな諦念に似た何かだった。
「わたしの魂は黙って、ただ神を待ち望む」
口をついて出たのは、記憶の底に沈んでいたその一行だった。今回は、歌としてではなく、現在の、この瞬間の、苦い現実として響いた。彼はゆっくりと呼吸を整えた。救いが、どのような形で訪れるかはわからない。もしかすると、このまま荒野で倒れるのかもしれない。しかし、ふと気づくと、追手への恐怖よりも先に、ある確信のようなものが胸の奥で微かに温もりを放っていた。人間の力は、天秤にかければ、ただの息に過ぎない。富も、権謀も、すべては移り変わる。変わらぬ岩、変わらぬ避け所は、ただ神だけだ。それは、状況が好転するという保証ではなかった。そうではなく、どんな状況のただ中にあっても、自分がそこに在ることを知っておられる方がいる、という事実そのものへの信頼だった。
夜明け前、彼は再び歩き始めた。目的地は定めていない。ただ、導かれるままに東へ向かった。足取りは重いが、心には奇妙な平穏が広がっていた。かつてないほどの飢えと渇きを感じながらも、それらが以前のように絶望に直結することはなくなっていた。彼は自分が、もはや何にもしがみついていないことに気づいた。全てを失ったからこそ、全てを支えるものに、初めて身を委ねることができる。
三日目の昼下がり、彼は砂漠の果てに、隊商の一群を見つけた。迷える者を拾うことをよくとする、遠くからの商人たちだった。彼らは言葉少なにエラムに水と食物を与え、ラクダの背に場所を提供した。救いは、劇的でも奇跡的でもない形で、静かに訪れた。隊商の長は、エラムの部族の事情を知り、中立の地への道を共にすると約束してくれた。
ラクダの背に揺られながら、エラムは振り返った。荒れ果てた故郷の地は、もう遠く霞んでいた。心には、複雑な思いが去来した。失ったものへの悲しみは消えない。しかし、その底に、岩のように確かなものがあるのを感じた。彼は目を閉じ、唇を動かした。
「神はわが岩、わが救い、わが高きやぐら。私は決して大きくは動かない」
「わたしの救いと栄えとは神にある。わが力の岩、避け所は神の中にある」
彼はそれを、囁きのように、確信を持って口にした。それは、状況が好転したからではなかった。むしろ、何も変わらない荒野のただ中で、彼自身の内側に、揺るぎない避け所が築かれたことを知ったからだ。風が砂丘を渡り、砂の波紋を描く。すべては移ろう。しかし、移ろうものの向こう側に、移らぬ慈しみがある。エラムは、これからも続くであろう人生の荒波を思った。それでももう、彼は岩の上に立っていることを知っていた。その岩は、彼の外側の状況ではなく、彼の魂の深みに据えられたものだった。夕陽が砂漠を赤く染め、隊商の影を長く引き延ばす。彼は静かに、次の一歩を踏み出した。