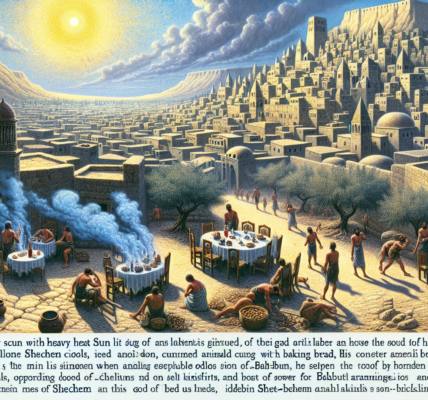夕暮れがエルサレムの丘を赤く染めていた。ヤケツエルは窓辺に肘をつき、眼下に広がる街のざわめきを聞いていた。ろばの鈴の音、商人の掛け声、どこかから聞こえる笑い声——すべてが、彼の胸に巣くう重苦しい静寂と対照的だった。彼は指でほこりをなぞり、深く息を吸った。油のランプが、壁に揺れる彼の影を不気味に長く引き延ばす。
今日も、また、法廷での光景が目に焼きついていた。未亡人となった娘のミリャムの土地を、隣人のショムエルが賄賂でねじ込んだ書類で奪おうとしている。裁判官は、ショムエルから贈られた上質な羊毛の外套をまとったまま、冷淡に証拠書類を流し読みしただけだった。「規定に従わねば」という言葉が、石のように冷たく響いた。ヤケツエルは唇を噛んだ。正義など、もはやこの地にはないのか。神よ、あなたはどこにおられるのか。
彼の心の中で、長年の信仰と、今まさに沸き上がる怒りの叫びが激しく絡み合った。詩を綴る習慣があった彼は、羊皮紙を広げ、尖った筆を握った。しかし、最初の一文字ですら、インクは滲んでしまった。
「復讐の神よ。」——彼の内側から湧き上がる言葉は、祈りというより、むしろ詰問に近かった。「いつまで、悪しき者たちは、いつまで勝ち誇ることが許されるのでしょうか。」
窓の外では、ショムエルとつながりのある若い役人たちの陽気な歌声が風に乗って流れてきた。彼らは、寡婦から取り上げたぶどう畑の収入で今夜も酒宴を開いているに違いない。その笑い声は、ヤケツエルには「神は見ておられない。我々の思いのままだ」と嘲るように聞こえた。彼らは、寄るべない者を圧迫し、異邦のごとく振る舞う。神の戒めなど、彼らの耳には届かない。いや、届こうとすら思っていない。
ヤケツエルは目を閉じた。ふと、幼い頃、祖父が語ってくれた出エジプトの物語を思い出した。葦の海が分かれたその日、神の腕は確かにあった。しかし今、その腕は見えない。ただ沈黙だけが、重くのしかかる。
「愚か者どもよ、いつ目覚めるのか。」彼は独りごちた。彼らは、耳を形作りながら聞かず、目を据えながら見ようとしない。民を造られた方が、彼らを懲らしめられないとでも考えるのか。諸国民を教えられる方が、知識をお与えにならないというのか。その考え自体が、あまりにも浅はかだ。
夜更け、ランプの炎が小さく揺れた。疲労が全身に染み渡り、彼はうつらうつらとし始めた。その時、ふと、かつての師である年老いたレビ人、エリアサフの言葉が蘇った。苦難の只中で、そのひだりの多い顔を輝かせて言った言葉だ。「ヤケツエルよ、主の懲らしめは、疎んじる者へのさばきであると同時に、御律法を愛する者には隠れ家となる。苦しみの季節は、私たちが自分の土台が何であるかを知るための時なのだ。」
はっと目を見開いた。闇の中、彼の思考は静かに、しかし確実に回転し始めた。神は、ヤコブを選ばれた。その民を、ご自身の嗣業とされた。そして、彼らの行いを、必ず尋ね問われる。悪しき者たちが、まるで野獣のように弱い者を罠にかけ、罪なき者の血を流すその行いを。彼らは「主は見ておられない。ヤコブの神は気にとめない」とほのめかす。しかし、その思いこそが、彼ら自身の盲目の証しではないか。
ヤケツエルは、ふと自分の心の内を省みた。この怒りは、単なる無力感から来るものなのか。それとも、神の正義への、歪んだ形ではあれ、どこかで信じる心の表れなのか。神が正義であられるなら、その正義は、時として待つことを要求する。人間の急躁な時計とは、針の進み方が違うのだ。
彼は再び羊皮紙に向かった。筆先が、今度は滑らかに動いた。
「民を戒められる方、知識を教えられる方。その方は、人の計らいのはかなさをご存知だ。主は、人の思いが、ただの息のように虚しいことを知っておられる。」
彼の筆跡は、初めの激情から、次第に確信へと変化していった。苦しみは、確かに彼を打ちのめした。しかし、打ちのめすだけではなかった。神の憐れみが、彼を見捨てなかった。闇が最も深い時に、かすかなともし火のように、ある確信が心に灯った。もし主の助けがなかったなら、私はとっくに沈黙の国、すなわち死の陰の地に下っていただろう。
彼は立ち上がり、窓辺に戻った。夜明け前の青白い光が、東の山々の輪郭をぼんやりと浮かび上がらせ始めていた。街はまだ眠っている。しかし、鳥のさえずりが、遠くで一つ、また一つと始まった。
「悪の罠が私に向けられても、私の魂は安らぎを見いだす。主は、私のよりどころ、わが岩となられた。」
ヤケツエルは、その岩のように堅固なものは、この世の法廷にも、賄賂にも、高ぶる者の力にもないことを悟った。それは、天地を造り、耳を持ち、目を据えられた方の内にある。その方が、諸国民を正し、悪しき者をその悪に応じて滅ぼされる。主は、私の砦。私の神は、わが避け所の岩。
彼は、まだ解決していない現実——ミリャムの土地問題、ショムエルの高ぶり——を知っていた。それらは消えていない。しかし、彼の内側にあった重石は、どこかで溶け始めていた。正義を執行するのは、自分ではない。自分の役割は、砦に立ち、避け所に身を寄せ、そして、与えられた場で、たとえ小さくとも忠実であり続けることなのだろう。
一番星が消え、東の空が淡いバラ色に変わり始めた。ヤケツエルは羊皮紙を巻き、机の上に置いた。そこに綴られた言葉は、完全な解答ではなかった。それは、闘いの記録であり、揺るぎないものへの、揺れ動く信仰の旅の一コマだった。
彼は深呼吸し、朝の冷たい空気を肺いっぱいに吸い込んだ。今日もまた、法廷には赴かねばならない。証言をし、弁明をしなければならない。結果はわからない。しかし、一つの確信があった。主の慈愛は、彼を支える。もしも、私の足がよろめこうとも、主の慈愛は私をささえられる、と。
窓の外では、新しい一日が始まっていた。光は、丘も谷も、正しい者もそうでない者も、等しく照らし始める。ヤケツエルは、その光の中に、目には見えない、しかし確かな約束の跡を、ほのかに見たような気がした。