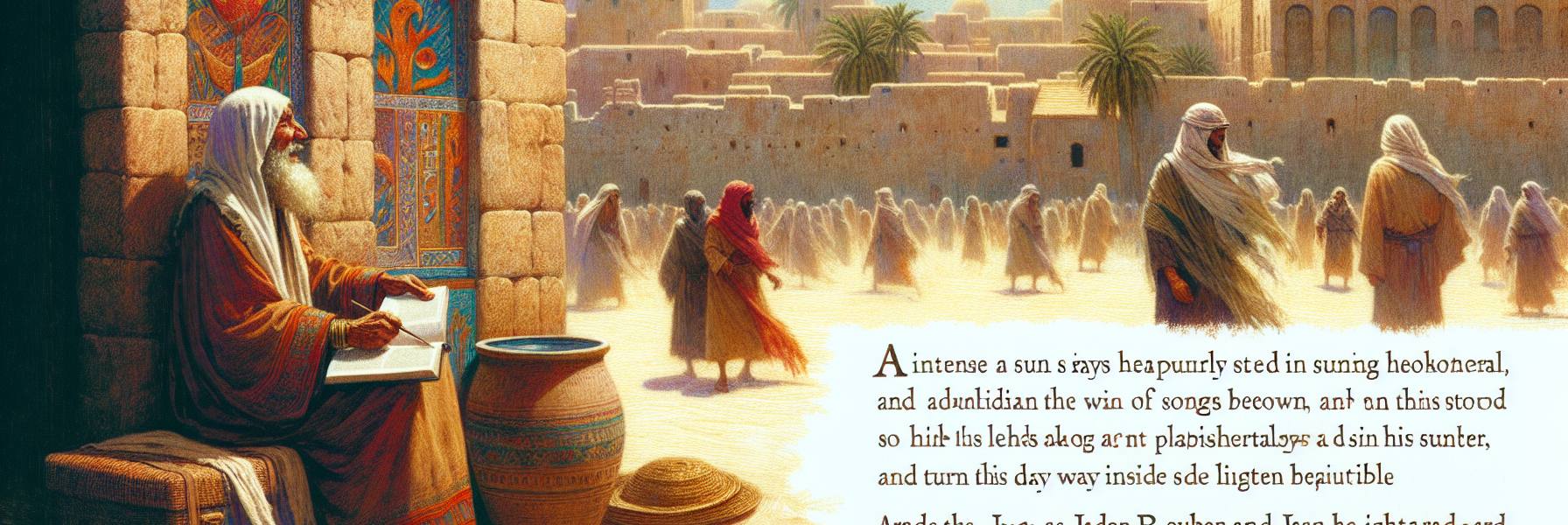朝もやがエルサレムの丘陵を覆い、羊毛のように厚く、冷たいときだった。私は城門の石段に腰を下ろし、夜明けの市場に集まり始める人々を眺めていた。足元では、夜露に濡れたざらついた石が、仄かに光っていた。
彼らはいた——油を塗ったような髪を揺らし、銀の腕輪をきらめかせて歩く者たちだ。高声で笑い、互いに背中を叩き合い、肥えた荷獣のようにのしのしと歩く。彼らの目には、この世の苦しみも神のさばきも映っていない。まるで、すべての幸せは手のひらで転がる小石のように、当然の権利であるかのようだ。一人の男が、細工を凝らした青銅の酒杯を掲げて何か叫んだ。周囲はそれに哄笑する。私は自分の粗末な麻の上衣の袖を見つめた。肘の辺りが擦り切れ、ほつれ始めている。
なぜなのか。
この問いは、私の胸の奥に、澱のように積もっていた。私は心を清め、手を洗い、あなたに従ってきた。夜明け前に祈り、定められたとおりに捧げものをし、言葉を慎んできた。それなのに、私の日々は苦しみに満ち、毎朝、新たな懲らしめが待っている。彼らは傲慢に生き、その富は増すばかり。健康は彼らに付き従い、死の恐怖さえ、遠く霞んでいるように見えた。
「確かに、私はむなしい思いに囚われ、愚かにもあなたの御前を歩んだ」
そう呟くと、喉の奥が熱くなった。この思いを口にすることさえ、共同体への裏切りではないか。人々に打ち明ければ、あなたの民を躓かせることになるかもしれない。だから私は黙って耐えた。しかし、その耐えるという行為そのものが、私を次第に蝕んでいった。心は荒れ、魂は干からびていく。まるで夏の渇いたワディの土のようだ。
ある真昼、灼熱の太陽が石畳を焼いていたときだ。私は偶然、彼らの一人が、弱い者を蹴落として商談をまとめるのを目撃した。その顔には、一瞬、冷酷な満足が走った。その瞬間、私の内にあった堰が決壊した。すべてが無意味に思えた。私の清くあろうとする努力も、私の苦しみも。この思いはあまりに重く、私を押しつぶさんばかりだった。
ふらふらと私は街を離れ、シオンの山へと足を向けた。なぜ、ここへ来るのか。答えはなかった。ただ、足が自然に聖所へと向かう。冷んやりとした石の影に入り、奥へ進むにつれ、外界の喧騒が次第に遠のいていく。香の煙がゆらめき、静寂が重く深く張り詰めていた。
そして、それは突然ではなかった。むしろ、長い間霧に包まれていた山頂が、風の一吹きで忽然と姿を現すように、理解が訪れた。
私は、彼らの終わりを見た。
そう、彼らは滑りやすい場所に置かれている。あなたは彼らを滅びの淵に陥らせた。彼らの繁栄は、瞬く間に崩れ去る幻だ。朝には威勢がよくとも、夕べには跡形もなく消えうせる糠のようだ。私が嫉み、心を悩ませていた彼らの姿は、実は滅びへと一直線に歩む、愚かな者たちの姿だった。私の愚かさよ。私は獣のように、目の前の餌しか見ていなかった。
あなたの御前を離れていたとき、私は苦く、傷ついていた。しかし、今、この聖なる場所で、私は悟った。あなたは私の右にいまし、私をとらえて離さない。あなたは私を導き、後には栄光をもって迎え入れてくださる。
天においてあなたのほかに、私にだれがあるでしょう。地にはあなたのほかに慕うものはありません。この肉も、この心も、尽き果てるときが来ようとも。
「しかし、神に近くあることは、私には幸いなことである」
私は静かに境内を後にした。外の光は相変わらず眩しかったが、もうそれは私を苛むものではなかった。坂道を下りながら、私は自分の足取りが、以前より確かなものになっているのを感じた。すべてを理解したわけではない。悪者が栄え、正しい者がもがく現実は、明日も変わらないだろう。しかし、一つの確かなことが、私の内に据えられた。それは滑ることのない岩の土台のようだった。
夕暮れが迫り、家々から灯りがともり始めた。私は自分の粗末な家の戸を開けた。そこには、僅かなパンとオリーブの油、そして一巻の羊皮紙があった。明日も苦労は続く。しかし、もう私はあの朝もやの中に佇み、彼らの輝きに魂をかき乱されることはない。あなたは私のとりえ、私の避け所。私の口は、あなたの御業を語り続けるだろう。
かつては苦さに満ちていた私の心に、今、静かな、汲み尽くすことのできない泉が湧き出ている。それは、この地上のいかなる幸いとも異なるものだった。