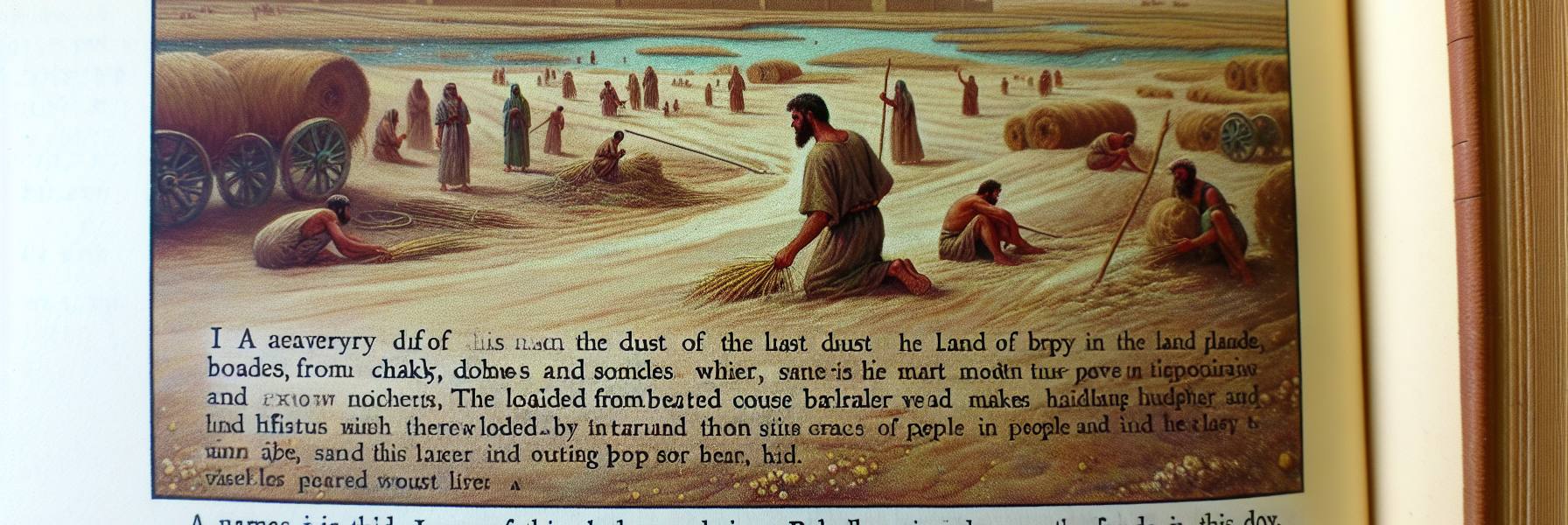その日、風は東から吹いてきた。砂埃が渦を巻き、バビロンの煉瓦造りの家々の間を、うなりながら通り過ぎる。窓という窓は閉じられ、わずかに布切れが垂らされた隙間から、うす暗い室内の様子が窺えるだけだった。アハブはその窓辺に座り、掌に積もった埃をじっと見つめていた。彼の指先は、かつてエルサレムの神殿の石材を磨いた時の粗さを、未だに残している。今、その手は何も造りはしない。ただ、捕らわれの民としての日々を、空しく数えるだけだ。
遠くで、川の流れる音がかすかに聞こえる。ユーフラテスだ。その川辺に、彼らは柳の木を植え、その枝に竪琴を掛けた。歌うべき歌は、シオンにしかない。口をついて出る旋律は、ただ涙に滲んで、異国の土に消えていく。アハブの妻、リブカは炉の火にかけた薄い粥を静かに混ぜていた。鍋の底から泡が立ち上がる音が、この沈黙に満ちた部屋で、不必要に大きな響きとなっていた。
「主は言われる」
突然、口をついてそう囁いたのは、年老いた隣人、オバデヤだった。彼は目を閉じ、皺だらけの手を膝の上に広げている。かつてエルサレムで書記の務めをしたその声には、今でも一種の権威が宿っていた。
「恐れるな、わたしはあなたを贖った。あなたの名を呼んだ、あなたはわたしのものだ」
アハブはゆっくりと顔を上げた。オバデヤは聖句を暗唱している。しかし、それは単なる記憶の反復ではなかった。まるで、その言葉が今、この埃っぽい部屋の空気を切り裂き、彼の耳に直接、注ぎ込まれてくるかのようだった。
「あなたが水の中を過ぎるときも、わたしはあなたとともにいる。川の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩んでも、焼かれず、炎はあなたに燃えつかない」
リブカが混ぜる手が止まった。彼女も聞いていた。ユーフラテスの水は、今、彼らを捕らえている。バビロンの炉の火は、日々、彼らの魂を焦がしている。そのただ中に、主が共にいると? それはあまりに遠い約束に思えた。アハブは胸の内にあった重い石のようなものが、ほんの少し、揺らぐのを感じた。
その数日後、町の広場で騒動が起こった。バビロンの役人が新しい布告を読み上げるという。人々はすすり泣き、あるいは怒りに顔を紅潮させて聞いていた。増税、そして神殿建設のためのさらなる労働力の徴用。アハブは群衆の後方に立ち、冷たい石壁に肩をもたせかけていた。絶望が、黒い油のように人々の間に広がっていく。彼は目を閉じた。その時、オバデヤの声が再び、心の内で響いた。
「あなたはわたしの目に尊く、貴く、わたしはあなたを愛している」
埃と汗と絶望の臭いに満ちた広場で、この言葉は何を意味するのか。尊い? この惨めな捕囚の民が? アハブは自分自身の埃まみれの足袋を見下ろした。貴くないものなど、ありはしないか。
しかし、夕方、日が沈み、狭い部屋に家族が集まって静かな食事を囲む時、彼はリブカが幼い娘ルツの髪を梳かす仕草を見ていた。そっと、慈しみを込めて。その指の動きの中に、何かが閃いた。愛とは、その対象の現在の価値によるのではなく、愛する者自身の選びによるのだ、と。主の愛とは、そういうものなのかもしれない。捕囚である前に、彼は「選ばれた者」なのだ。この状況を決定づけるものは、バビロンの王の布告ではなく、もう一つの、より深い宣言なのだ。
月日は流れた。ある春の夕暮れ、アハブはたまらず家を飛び出し、町外れの小高い丘に登った。彼は息を切らしながら頂上に立ち、西の空に広がる燃えるような夕焼けを見つめた。そこへ、東から闇が迫ってくる。光と闇のせめぎ合う地平線。彼は突然、自分がこの両方のただ中に立っていることを悟った。捕囚の闇。しかし、その闇でさえ、主が新しいことをなそうとされる場なのではないか。
「見よ、わたしは新しいことを行う。今、もうそれが芽生えている。あなたがたはそれを知らないのか」
風が丘を吹き抜け、彼の外套をはためかせた。この風は、東からではなく、どこからともなく吹いてくる。新しい風だ。彼の心に、長く眠っていた何かが動き始めた。それは希望というにはあまりにぼんやりとした、しかし確かな感触だった。彼はバビロンの町並みを見下ろした。確かに、彼らはここに捕らわれている。しかし、主が共におられるとすれば、このバビロンでさえ、通過点に過ぎない。ユーフラテスの水も、いずれは背を向けて渡る日が来る。その時、水は両側に壁をなすだろう。
「あなたがたはわたしの証人だ」
オバデヤがよく口にした言葉だ。証人。それは単に過去の奇跡を語り継ぐ者という意味ではない。今、この腐敗と絶望のただ中で、なお「わたしがそれだ」と宣言される主を、その存在そのもので証しする者。アハブのこの捕囚の生活、彼の沈黙、リブカの粥を炊く日々、ルツの無邪気な笑い、隣人オバデヤの聖句の暗唱——それらすべてが、もし主と共にあるなら、証言となるのだ。
彼はゆっくりと丘を下りた。道すがら、川辺の柳の木を見た。枝には、いくつかの竪琴が未だに掛けられたまま、風に揺れていた。ふと、彼はある考えが浮かんだ。明日、その竪琴を一つ外し、埃を払い、弦を調べてみようか。歌うべき歌は、確かにシオンにある。だが、シオンを歌う心は、今、この場にもある。主が共におられるなら、このバビロンの地でさえ、歌のための場所となる。
家に戻ると、リブカが灯芯をいそいそと整えていた。ほのかな油の灯りが、彼女の横顔を柔らかく照らす。
「どこへ行っていたの?」と彼女が聞いた。
「少し、歩いてきた」とアハブは答えた。そして、炉端に座り、温まりながら言った。「オバデヤさんの覚えておられるあの言葉… 水の中を通るときも、共にいると言われたあの言葉だ。あれは、単に過ぎ去った昔の約束ではないような気がしてきた」
リブカは手を止め、夫を見つめた。彼の目に、久しく見なかった静かな光が宿っているのを見て取った。
「今、私たちが通っているこの『水』の中にも、主はおられる。そして、いつか、私たちがこの水を渡り終えるその時まで」
彼は言葉を続けた。それは、彼自身にとってさえ、新しい確信だった。
「私たちは証人なんだ。この闇の中でも、主が主であられることを証しするために、ここにいる」
次の日、アハブは実際に川辺へ行き、柳の枝から一つの竪琴を丁寧に外した。家に持ち帰り、乾いた布で丹念に拭い、ねじれた弦を一本一本、慎重に調べた。最初は軋むような音しか出なかったが、次第に澄んだ、かすかに震える音色が部屋に満ち始めた。
彼は歌わなかった。まだ、歌うには早すぎた。しかし、その音色そのものが、彼にとっては一つの宣言だった。イザヤの言葉は、遠い預言者の書物の中に封印された過去のメッセージではなく、今、この埃っぽい部屋で、弦の震えと共に甦る、現在への呼びかけだった。
「恐れるな。わたしはあなたと共にいる」